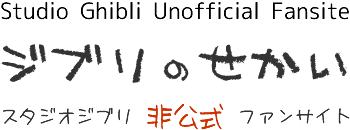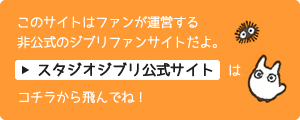高畑勲監督が『火垂るの墓』について語ったインタビューを文字に起しました。
2015年に行なわれたもので、本作を描くことになった経緯や、監督自身の戦争体験などを語っています。
戦争中は悲惨だけではなかった、喜びも楽しみも自由もあったと高畑監督は語ります。
一昨年公開されて高く評価された『この世界の片隅に』がまさに、その空気感を描いていましたね。高畑監督の『火垂るの墓』は、戦争映画の源泉ともいえる作品になっているかもしれませんね。
表現上の野心が強かった
高畑:
そんなにぼくは、野坂昭如を知ってたわけじゃないんですよね。プロデューサーをやっていた鈴木敏夫って人は、そういう世代なんです。それに対してぼくは、何に惹かれたかというと、独特の求心力なんですね。野坂さんの原作は、心中モノの構造をもっていてね。しかも、非常に閉じた世界なんですよ。
その心中モノみたいな構造っていうのは、これはひょっとしたらアニメーションというものの表現で、意味のあるものが作れるんじゃないかと思った。いわば、表現上の野心のほうが強いんですよ。それから、もうひとつは、自分が空襲を経験しているということですね。
空襲シーンは実体験
高畑:
空襲の逃げ方からいうと、おそらくあの二人より、ぼくと上の姉のほうがずっと危険で、死んでもおかしくなかったです。
周りがボーッと燃えていたんで、反対側に逃げたんですね。その反対側っていうのは、町の中心部だったんですよ。そうすると、そこにドンドン焼夷弾が降ってくるでしょう。
また逃げると、そこが既に燃えていたりして、それこそ火の海の中に入ってしまったんだよね。よくぞ助かったと思いますけど。
そういうことを自分自身も経験しているわけですから、そういうものを描く基盤にあったでしょうね。
戦時中も人間ドラマはあった
高畑:
戦争中のことを、今の人は捉え間違える危険性があるのは、悲惨な時代だと思ってるけど、人間は悲惨だけじゃ生きられないです。だから、喜びも楽しみも、自由もあるわけです。要するに、子どもっていうのは、それを見つける天才ですから。だから、それも描いたつもりなんですね。ある意味、淡々とだけど、事実を描いたほうが良いと思いますね、悲惨な状態そのものを。
つまり、「悲惨でしょ? ちょっと涙を流してください」って描き方をするつもりは、全然なかったんですけど。もっと、戦争の悲惨さを出すんだったら、もっと激しくやらないとおかしいんじゃないかとかね。あるいは、実際にそのあとのドラマや映画なんかで嘘をついてますよね。それは凄く気になるんですよ。
絶対に足を踏み入れちゃいけない
高畑:
「愛する家族のために戦う」とか、その当時は言ってなかったんだけど。しかも、コロリとみんな騙されていくわけですね。観る側も、そう言われると安心するんですね。主人公のヒロイックな行動に、良かった泣けたって言いたいから。映画を観に行く目的がそうだから。
例えば、戦争に反対していた人も、一旦戦争したら日本国を応援するしかないと思うんですよ。もう勝ってくれるしかない。負けたら悲惨なことになるに決まってるからね。空気読むんですよ、皆さん。若い人が。
だから、日本国の空気を読んで、そうなるに決まってるじゃないですか。なりやすいじゃなくて、なることに決まってるから、絶対に足を踏み入れちゃいけないんだって、そこに。