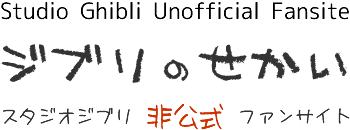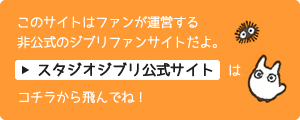第87回米アカデミー賞で長編アニメ部門にノミネートされていた『かぐや姫の物語』での受賞は惜しくも逃しましたが、アメリカのロサンゼルスで高畑勲監督と西村義明プロデューサーが会見を開きました。
第87回米アカデミー賞で長編アニメ部門にノミネートされていた『かぐや姫の物語』での受賞は惜しくも逃しましたが、アメリカのロサンゼルスで高畑勲監督と西村義明プロデューサーが会見を開きました。
同賞を受賞したディズニーの『ベイマックス』をはじめ、アニメーションの世界ではCGが全盛の時代。手描きのタッチにより、観客の想像力を引き出す作品づくりにこだわる高畑監督は、“平面アニメ”への強い思いを語りました。
多くの作品が3DCGになっている。
受賞できれば、平面の絵で物語を表現する火が消えにくかったので残念。
――アカデミー賞の感想をお願いします。
高畑:
面白いイベントだったんですけど、残念ながら取れませんでして。せっかく集まっていただいたのに、期待に応えることができなくて、すみませんでした。それは、しょうがないですね、運だと思ってましたから、最初から。対抗馬もだいたい観たんですけど、すごく良い作品が多かったし、どうなるか分からないと。だけど、非常に残念なのは、やっぱり多くの作品が立体なんですね。3DCGとか、あるいはストップモーションによるものとか。それに対して、平面の絵で、物語を表現するということが、もしここで認められたら、そういうものの火が消えにくいだろうと。あるいは、これからも隆盛になること起こるかもしれないと思うので、そういった意味では残念ですね。それから、もう一つは、ノミネートされたから、非常に期待が高まってですね、ほんとうに互いに努力をしたスタッフが、それなりに期待もしていたはずなんで、それが残念ですね。でも、改めて考えれば、ほんとうにみんな頑張ってくれたということを、改めていま思います。
西村:
めちゃくちゃ悔しいですね。取りたかったですよね。ほんとうに、この作品は長い時間が掛かったんですけど、作品に取り掛かるときに、スタッフを誘う必要があって、そのスタッフには、「高畑勲監督をアカデミー賞に連れて行きたい」ということを、ぼくは公言していたので、それが叶ったし、高畑さんという素晴らしい才能がアメリカで認められて、そしてその隣に居られることを、とても光栄に思っています。
――3日前に座談会があったと思いますが、そのときの感想をお願いします。
高畑:
英語が喋れないだけじゃなくて聞き取れないので、シンポジウム全体が分かったわけじゃないんですが。ただ、もちろん通訳はしてもらったので、シンポジウムそのものはたいへん面白かったですね。みんな、やっぱり、それぞれ自信を持って作品を作ってきて、それを語り合うことが出来たので。西村君が、非常に素晴らしい発言をしてたので、それを聞いてもらいましょう。
西村:
なんでしたっけ?(笑)
高畑:
ほら、日本のアニメーションの影響がって(笑)。
西村:
あぁ、今回ノミネートされた、『かぐや姫の物語』以外の4作品を、アメリカに来る前に観たんですけど、スタジオジブリの影響がほんとうに色濃くて、オリジナルは『かぐや姫の物語』だけじゃないかと思ったりもしたんですけどね(笑)。その影響があるっていうことと、ただ悪い意味ではなくて、高畑さんとか宮崎さんが作ってきた作品が、日本だけじゃなくていろんな国の、いろんなクリエイターに影響を与えているってことが見て取れたので、ほんとうに凄いことだなと。ほんとうに素晴らしいと思いました。
あと、高畑さんが一言しゃべるたびに、会場がみんな拍手するんですよね。『かぐや姫の物語』高畑勲という人物に対する、凄いリスペクトを感じて、あのシンポジウムが終わったあとに、高畑さんのところだけに100人ぐらいの観客が押し寄せて、サインをねだったりしていて、ほんとうに高畑さんへの敬意を凄く感じました。
――『かぐや姫の物語』がノミネート作品になり、高畑さんの築いた手法が、海外の人に認められたというのはどういう気持ちですか?
高畑:
それは、嬉しかったですね。嬉しかったんですが、非常にずうずうしく言えば、たぶん入るんじゃないか、って気はしてましたね。
要するに自分というより、あの努力は世界全体のアニメーションから見渡しても、あの手法を、あれだけやり抜けたというのは、やっぱり評価されるべきじゃないかと。自分じゃなく、スタッフというのかな、その力を感じていますので。
――他にも映画祭はありますが、それとアカデミー賞と何か違いはありますか?
高畑:
今まで外国のコンペに出したことが、あまりないんですね。スタジオジブリの方針も、必ずしもいつも同じだったわけじゃないんじゃないかと思うんだけど。『平成狸合戦ぽんぽこ』っていうのが、アヌーシーで長編賞を受賞したんですね。そのときは、ぼくがフランスに親近感を感じていたことと、それからアヌーシーっていうのは、歴史を振り返ると、実に反旗をひるがえした連中が作り始めた映画祭でね。そこで受賞したことは、嬉しかったですね。
アカデミー賞に関してはですね、実は『千と千尋』がアカデミー賞を取ったときに、やたら「アカデミー賞を取った取った」と言うんで、ぼくは「違うんじゃないか」と言ってたんです。というのは、どういうことかというと、ベルリン映画祭で金熊賞を取ったほうが、ずっと大きな意味があるだろうと。なぜなら、アニメーションの中で競争したのではなくて、あれは「映画全体」ですからね。その中で、認められたというのは、アニメーションのステータスの中で、非常に大きな意味があったと、ぼくはあのとき思いました。ほんとうに、「おめでとう」と言いたかったですね。
ディズニーは歴史が長い。
浮き沈みはあったが、ここにきて大きな影響を与えるようになっている。
――今回受賞した『ベイマックス』、前回の『アナ雪』、いずれの監督もスタジオジブリに影響を受けています。その辺りはどう感じていますか?
高畑:
それは、そう言って下されば、くすぐったいけど嬉しいですね。それ以上は、ちょっと分からないですけど。でも、お世辞じゃなくて、『アナ雪』も面白かったですね。ただ、あんなに爆発的になるのは、予測がつきませんでしたけど。今度の『ベイマックス』も面白かったです。そういう意味では、「なんで、あんなのが取るんだ」って気がしてるわけじゃないんです。もちろん、自分たちのが取れなかったのは残念ですけど。
ディズニーっていうのは、歴史がずいぶん長いですから。その間の浮き沈みや、人に与える影響が違ってきたんだけど、ここにきてディズニーは、また大きな影響を与えるようになるんじゃないですかね。
――影響を与えているのが、スタジオジブリの作品なんじゃないかと思うのですが。
西村:
この10年間で、ディズニー・ピクサーは、スタジオジブリを研究しつくしたんでしょうね。その研究しつくした成果を、『ベイマックス』に見ることができて、……焦ります。ぼくらは、もっと先人たちに学ぶことがあるし、それはスタジオジブリだけじゃなくて、今のピクサーにも。それこそ、この作品に影響を与えた、フレデリック・バックさんというアニメーション作家にも。いろんな方々に学びながら、新しいものを作っていかなきゃいけないなと、ほんとうに思いますね。
日本人は立体的に捉えるのが得意ではない。
絵の表現を、なんとかして良いものにしていきたい。
――今回受賞すれば、「平面で描くことの火が消えなかった」という発言の詳しい意味をお願いします。
高畑:
火が消えなかっただろう、と言ってるんじゃなくて、ある意味では消えかけているわけじゃないですか、世界的にみて。日本は続いているんですけど。しかし、日本もなにかの形で打開しなきゃいけないということを、ぼく自身もずっと思っていて、そのスタートとして田辺修と組んだのが、『となりの山田くん』だったんですよ。それで、『かぐや姫』をやったんです、同じ田辺君で。そういうことで言うと、同じ平面で描くのでも、もう一つ別の意味を……しょっちゅう言ってるんですけど、「人の記憶を呼び起こす」とかね。要するに、刺激するという絵柄にならなきゃいけないだろうと。それを実践しているつもりなんですね。だから、そういう形で、生き延びていく必要があると思うんですよ。要するに、絵であるということですよね、平面っていうのは。絵の持っている力っていうのは、今度のような絵だけじゃなくて、いろんな絵があり得ると思うんだけど。絵の持ってる力そのものに、ものを言わせるべきで。一方、3DCGとかになると、絵じゃなくなっているでしょう。ディズニーの中でも、携わっている絵描きは、たくさんいるんですよ。ところが、いつの頃か聞いたんですけど、自分たちもほんとうは絵をやりたいって。絵描きなんだから。ところが、それが立体になってしまうでしょう。そうすると、残念な部分もあるはずなんですよ。そういうことで言うと、大事なジャンルとして、絵による表現は、なんとかして良いものにしていきたいと思ってます。そのために、オスカーが取れたのと、取れなかったのでは、取れたほうが良かっただろう、という意味です。
――今後のアニメーションはどのように変化すると思いますか?
高畑:
ですから、今言ったように、いろんなことが出来得ると思うんですね。可能性っていうのは、無限にあるわけですよ。ただ、それが作りやすいとか、作りにくいとかね。例えば、立体が流行り始めたら、どんどん立体に行かざるを得ないとかね。日本の風土とか、歴史的な積み重ね、日本美術史と言ってもいいですけど、ものの見方ですね。それをどういう表現にするかということについて、いろんなことを考えた場合に、立体が必ずしも西洋人に比べて得意ではないんじゃないかと思うんです。どういうことかって言いますと、完全にファンタジーの世界を作りあげて、立体で。それは、ほんとうに見たことがないものを作るのだから、立体は非常に意味がありますね。ところが、日本の場合、漫画も含めてですけど、ごく平凡な日常生活とか、そういうのが舞台になって、そこにファンタジー要素が持ち込まれるものが多いわけじゃないですか。そうすると、そういうものって、立体にしてしまったら、別世界になっちゃいますよね。だから、それを現実的に描こうと思ったら、実写のほうが良いんじゃないかって話にならざるを得ない側面があるんですよ。だから、いわゆるファンタジー、元々ファンタジーというものを作るのが好きなのか、日本の私たち及び観客が。そこらへんが、また問われてくると思いますね。
――監督はアニメーションを、あらゆる芸術表現のなかで、物語を伝えるうえで最高のものだとお考えでしょうか?
高畑:
そんなこと思ってないですよ。普通の映画も素晴らしいしね。いろいろあると思うんですよ。
――将来のアニメについて、西村さんは?
西村:
CGアニメーションが主流になるでしょうね。CGアニメーションが主流になったときに、今度はコンピュータグラフィックスと実写の境い目がなくなるでしょうから、アニメーションというジャンルが、よく分からないジャンルになっていく気がしますね。
今回のノミネート作品で『ヒックとドラゴン2』っていうのが、前作に比べて動きがリアルになってるんですよね。そうなってくると、このキャラクターをCGで見るのと、実写で見るのとで、何か変わってくるだろうかということが出てくる。例えば、『ポーラー・エクスプレス』という映画と、『クリスマス・キャロル』って映画とかあるんですけど、あれはモーション・キャプチャっていう、人間の動きで作ったんですけど、それと『ヒックとドラゴン2』の動きっていうのは、果たして何が違うんだろうって。実写で出来ること、出来ないこと。アニメーションで出来ること、出来ないことっていうのを、作り手たちが考えて、どういった表現ができるか考えながら作っていく時代に入るんだと思います。
アメリカは個人主義だが、チームを作る力がある。
日本は同調気質だが、個人的にやっている。
――世界各国のアニメーターとかファンに会って、制作意欲が上がったかなと思うんですが如何ですか?
高畑:
それは、変わらなかったですね(笑)。頑張ってる人たちと会ったりしたのは、それは嬉しいことで、面白いと思うんですけど。作りたいってことは……、ぼくは作れるかどうか分からないし。また別の問題として、頭の中では考えますけど。
――次回作を楽しみにしています。
高畑:
ありがとうございます。
――西村さんは、先ほど「焦る」とおっしゃっていましたが、今後のジブリについてどのようにお考えですか?
西村:
一本一本の作品に関して、「焦る」って思ったんですけど。焦るっていうのは、今回ノミネートされたクリエイターと話すなかで、ほんとうに皆さんがアニメーションを愛してるし、自分たちが作ったもの、自分たちの作品のチームメート、メンバーですね。それと、スタジオを支えてくれている会社の人たちにも、みんなに敬意を払っていて、自信を持ってるんですよね。そういうチームを、日本で絶対作っていかなきゃいけないし、残していかなきゃいけないって気持ちは、強く持ちましたね。そういう意味で、「焦る」と思いました。
高畑:
今の話のついでに。今彼が言ったけど、チームっていうのは、こちら(アメリカ)のほうが基本的に個人主義ですよ。日本のほうが、同調気質で。そのくせに、チームを作る力があるんですね。例えば、脚本なんかでも複数でやるでしょう。やっぱり、娯楽作品を作るときは、非常に有効に働くわけじゃないですか。面白く見せるっていう。むしろ、日本のほうが個人的にやっているわけでね。それから、スタッフの集まり方なんかも、そういうとこがあるんですよ。誰かがやると、貸し借り関係みたいになってね、「おれが今度やるときには、手伝ってもらう」って。一丸となって、この作品を盛り立てるというより、借りを返すっていう形で参加してくる。そういうふうな意識が強くて、そこらへんで心配が、彼(西村)にあるのは当然だと思いますね。
こういう場だから言うんですけど、外国のメディアに、田辺修っていうのと、男鹿和雄って名前を挙げてきたんです。それは当然なんですね。ああいうスタイルっていうのは、理念としてはだいぶ前から話してもいたし、持っていたんだけど。そういうことが実現する人って、そう簡単にいないんですよ。田辺修と男鹿和雄っていうのは、日本にとって凄い才能だし、おそらく外国から見ても大きいと思うんですね。その人たちの協力があって、初めて出来たんでね。これからは簡単なことじゃないんでね、非常に恵まれたことっていうのは。この仕事(かぐや姫の物語)っていうのは、「みんな」ですけれど、言うならば、ぼくと、その二人。この三人が大将としてやった仕事だと、はっきり思ってます。
西村:
アカデミー賞の授賞式が終わったあとに、ガバナーズ・ボールっていうとこに行って、パーティーがあったんですけど、そこで高畑さんとクリント・イーストウッドと、ぼくの三人で写真を撮りました。それはもう、忘れられない思い出です。イーサン・ホークにもハグしましたけど(笑)。
――それは、とても大事なことですね(笑)。ありがとうございました。
 |
高畑勲、『かぐや姫の物語』をつくる。~ジブリ第7スタジオ、933日の伝説~ アニメーション映画監督・高畑勲。その14年ぶりの新作『かぐや姫の物語』の制作現場に約2年半にわたって取材。 その制作過程と高畑演出の現場を明らかにする。 |