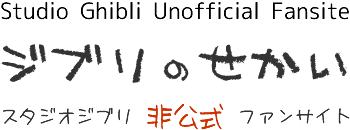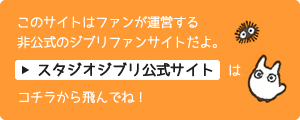『かぐや姫の物語』で、高畑勲監督らと苦楽をともにしてきた西村義明プロデューサーのインタビューが、WEBアニメスタイルに掲載されています。
『かぐや姫の物語』で、高畑勲監督らと苦楽をともにしてきた西村義明プロデューサーのインタビューが、WEBアニメスタイルに掲載されています。
『かぐや姫の物語』の創作にまつわる裏話が語られています。西村プロデューサーが、ここまでディープに語ったインタビュー記事は、あまりないと思います。
線の向こうにある本物を
── いきなり的外れな質問かもしれないんですが、今回の『かぐや姫の物語』は、20世紀末に高畑さんが企画していた「絵巻物のようなアニメーション」とは、別物の企画なんですか。
西村:
それとは別物です。「平家物語」を鳥獣戯画でやるという企画が、僕が担当になる前にはあったみたいですけど、企画としては随分前に潰えています。僕が担当に就いた頃には、そういう話は一切なかったですね。
── なるほど。
西村:
日本のアニメーションが、絵巻物や浮世絵といった日本の絵画の流れを汲んでいる、みたいな話は高畑さんとよくしていました。ただ、具体的に「絵巻物みたいなアニメーションを作りたい」という話は一度もしていませんね。
── すると『かぐや姫』という題材を選んだ段階で、今のスタイルになった?
西村:
いや、違います。これはもう『(ホーホケキョ となりの)山田くん』のあとから、この描線で、スケッチ風の淡彩の画面でやりたいという意志が、高畑さんの中にありましたから。企画がどんなものになろうと、このスタイルで作ることは決まっていました。高畑さんって、いつも「表現と内容は必ず一致していなければならない。作り手はそれを考えるべきだ」と言ってますよね。だけど、今回の作品に関しては、この表現が先にあった。
── 現場では、高畑さんがどうしてこの画でやりたいかという話をされたりしていたんですか。
西村:
ずっとおっしゃってましたね。「線の向こうにある本物を」と。人形アニメなんかは、実在するものを1コマずつ動かして撮っているじゃないですか。そうすれば当然「実在感」は得られますよね。本当に人形はそこに存在するんだから。フルCG立体アニメーションも、バーチャルに作られたものですけど、それを実在させるべく仮想空間に置き、影をつけたりして動かしているわけです。そうすると本当に実在しているかどうか、つまり、今見ているものそのものが本物らしいかどうかを観客は意識しちゃう。それがいいか悪いかは別にして、たとえピクサーのように様式化されていても、ある種の「リアルさ」を追求せざるを得ないのではないかと。
高畑さんとしては、その逆に行けないかという考えがあったんでしょうね。本物を見ながら、それをスケッチに落とし込んでいく。そうやって、ある動きの一瞬一瞬を捉えたスケッチ的な絵を何枚も重ねていく様式。その線で描かれたそのものが本物だと主張するわけではなくて、そのスケッチ的な描線の向こうに、絵描きが捉えようとした本物を想起させるような画面は作れないだろうかと。
── 確か『おもひでぽろぽろ』の頃に、高畑さんが『じゃりン子チエ』を例にしておっしゃっていと思いますが、例えばあるしぐさをアニメーターが観察して、自分の中に一旦取り込んでから紙の上に出力することによって、いかにもそれらしくなるんだ、と。ロトスコープのように実写映像をそのままなぞるわけではなく、いちどアニメーターのフィルターを通して出力されたものが本物の表現になるんだ、といった話をされていました。そういうことでしょうか。
西村:
多分、通じる話だと思います。高畑さんは、ご自身の作品を「クソリアル」と表現することがあるんです。リアルには「リアリズム」と「リアリティ」があるじゃないですか。高畑さんって、ある時期まではリアリズムを追求してきた方だと思うんですよね。『おもひでぽろぽろ』なんかも、いろいろ整理はされてますけど、やっぱりリアリズムで描かれている。でも、それから時を経て作られた『山田くん』は、リアリズムじゃないですよね。あれはリアリティだと思うんですよ。
(略)
── 高畑さんは、セル画と背景の組み合わせでリアリティのあるアニメを作る手法を確立して、それを理論化した人じゃないですか。そういう手法に関して、高畑さん自身は「やり尽くした」みたいな意識があるんでしょうか。
西村:
いや、そういう「やり尽くした」とか「100%できた」みたいなことは絶対に言わない方ですから。自分のなかで、ある程度は到達できたという感覚はあったでしょうけど、その先に何があるのかということに関しては、懐疑的だったんでしょうね。90%できているものを100%にする作業に、あまり面白さを見出さないということだと思います。「(その先に)何かあるのかな、面白いものが」とは、常日頃から高畑さん自身がおっしゃっていましたし。
── ご本人がそうおっしゃっていたんですね。
西村:
うん。「もうジブリ・アニメみたいなものは絶対やりたくない」ともおっしゃってました(笑)。
田辺修が納得するまで映画は作らない
西村:
僕が思うに、田辺さんって、デフォルメされたものを人間らしく動かすことにかけては右に出る者がいないと思うんですよ。もちろん、読売新聞の「瓦版編」(編注:読売新聞社の企業CM)みたいなものを描かせてもすごいんですけど、「どれどれの唄」のPVとか『ギブリーズ episode2』の田辺さんパートとかは、似たようなところにあると思うんですよね。
── 「どれどれの唄」って虫のキャラクターがいっぱい出てくるやつですよね。
西村:
そうです。歌っている拝郷メイコさんを模したような女の子がギター抱えて歩いてて、その手足がグニャグニャになってるんですけど、あれはまさに「あ、感じ出てるなあ」ってやつですよね。心地いいときって、こうやって足をふわって振り上げて歩くよな、っていう。そういうものを描かせたらすごいですよね、あの人。『山田くん』も同じところにあると思いますよ。とにかく「感じ」を掴むのがうまい。そこを高畑さんはいちばん評価してますよね。まあ、ひと言で言えば天才なんですね。
── で、田辺さんは『かぐや姫』では動いたんですか。
西村:
結果としてですね。それまでは本当に動かなかったんですよ。ある時期、僕の前任者と高畑さんが「竹取物語」……つまり、のちに『かぐや姫の物語』となる企画を考えていたんですけど、もう全然動かないので、僕が担当に就かされるんです。企画の骨子自体は、55年前に高畑さんが着想した「竹取物語」のプロットがもうあるわけですから、それを具体的にしていけばいいわけですけど、全然具体にならないんですよ。画を描かないから。田辺さんは1年半ぐらい『かぐや姫』には関わってるはずだし、ご自身でも「自分がジブリに残っているのは高畑勲監督の作品をやるためだ」と言っているのに、1枚も画を描かなかった。そんな状況で僕が投入されたんですけど、4ヶ月ぐらい経った頃かな? 僕はまだ投入されて間もなかったから「まあ、これからだろう」と思っていたけど、トータルで言えば2年間ぐらい動いてないわけですからね。鈴木敏夫プロデューサーが来て「田辺君が画を描かないんだったら、田辺君が画を描ける企画にしなきゃいけないだろう」と。
── なるほど。
西村:
そのとき、田辺さんは明治時代について大塚伸治さんと研究してたんですよ。本人は「研究なんかしてない」と言ってますけど。
── 明治時代ですか。
西村:
そう。明治時代の女性のしぐさとか、人の歩き方とか。その研究成果は、読売新聞の「瓦版編」にも部分的に表れていると思うんですけどね。なぜ明治時代かというと、明治までだったら写真資料とか映像資料をもとに、実感のこもった芝居が描ける。だから明治までが限界だ、と言っていたんです。だとしたら、明治以降を扱ったものにしなきゃいかんということで、鈴木さんが出してきたのが「山本周五郎の『柳橋物語』はどうだ」というアイデアだった。舞台は江戸末期なんですけど、明治と近いから大丈夫だろうと(笑)。
(略)
コンテ作業の長い旅
── コンテの段階でも、かなり完成した作品に近い画面にはなってますよね。
西村:
そうそう。ラフ原みたいに割ってるところもかなりある。普通のコンテよりも全然割ってるんですよね。
── それでもレイアウトや原画で直しを入れる。そのために、田辺さんのチェック待ち状態になるわけですね。
西村:
そうなんですよね。田辺さんがよく言ってましたけど、巧い原画さんはミリ単位で線を選んでるから、QAR(クイックアクションレコーダー)で撮るときもタップ穴がズレたりしないように気をつけてくださいと。でも、田辺さんはミリ単位じゃないんです。0.1ミリ単位なんですよ。この線のこの感じが違うだけで、画の印象が全然違うというのが分かってる。
── ラフな画でも。
西村:
全然違いますね。線の濃淡、線の出と入り。この線は太く、この線は細くとか、そういうのは理屈を超えた「センス」ですからね。そのセンスを全面的に活かそうという作品だから、まあ、最初から大変なことになる宿命を負ってたんでしょうね。僕は、その大変さを全然分かってなかった。
── ……おつかれさまでした(笑)。
西村:
いやいや、大変だったのは僕だけじゃないですから。
── コンテも、田辺さんと高畑さんの2人で作られていったんですよね。
西村:
まあ、そういうふうに言うと簡単に聞こえますけどね。高畑さんとしては、コンテの前にイメージボードを描いてほしかったんですよ。それで、脚本作業を始めたとき、田辺さんにも参加してもらったんです。イメージが湧かないから描けないと言うのなら、その場で話を聞いてイメージを得てもらうしかない。それで、高畑さんの家でずうっと脚本会議をやっていたんですけど、それでも田辺さんは描いてくれなかった。
── 監督のご自宅でやっていたんですか。
西村:
ええ。ジブリが準備室を設けさせてくれなくて……。みんな、この企画ができるとは思ってませんでしたから。
── そのときの『かぐや姫』スタッフは?
西村:
僕と、高畑さんと、田辺さんです。
── 3人だけ?
西村:
そうですよ。それで、脚本会議をやってもイメージボードができないし、キャラクターもできない。田辺さん、匿名の髪の長い女性とかは描いてくるんですけど、かぐや姫のイメージとは程遠いわけですよ。それでも、イメージボードらしきものを8枚ぐらい描いてきたのかな。いずれも抽象的なものでしたけどね。それを高畑さんに見せたら、また激怒ですよ。「なんですか、これは」「いや、試しにイメージボードを描いてみたんですけど」「この四角はなんですか」「いや、フレームのつもりなんですけど」「フレーム? フレームっていうことは、これが完成画面のつもりで描いたってことですか」「そのつもりです」って。
── ハラハラしますね……。
西村:
「あなたねえ……これで映画ができると思ってるんですか!」って、そこからバーッと怒り出すんですよ(笑)。「大体ね、画が少なすぎるよ! もっと描いてきてよ!」って。
── そういう言い方をするんですか。
西村:
うん。それで田辺さん、また描かなくなったんですよね(笑)。高畑さんに怒られてから、イメージボードは一切描きませんでした。キャラクタースケッチみたいなものは、すーっと描くんですけどね。だけど、世界が広がっていかないじゃないですか。それでずっと高畑さんは田辺さんのことを怒り続けてるしね。どっちもどっちですよ、僕からすりゃあ。
(略)
── 役者の声の芝居に、高畑さんの演出が反映されているわけですね。
西村:
声っていうのは、やっぱりイメージを喚起する力があるんでね。実際、それによって田辺さんはコンテ上で姫の表情をつけていけたし、作画にしても声に引っ張られていったところは多々あったでしょうね。地井(武男)さんの「ひーめ! おいで!」なんていうところは、プレスコ現場で聞いていたときは生々しすぎて、アニメーションには向いてないんじゃないかと思ったんですよ。高畑さんもそう言ってましたし。あの生々しさは、田辺さんがうまかったから拾えたんでしょうね。
── あそこは、コンテが先にあった?
西村:
序盤だから、コンテはあったかもしれません。でも、プレスコではコンテじゃなくて脚本を見ながらやってますから。
── 地井さんの芝居に合わせて、コンテを変えたりもしているんですか。
西村:
確かにコンテよりも尺は伸びてるんですけど、地井さんの芝居が長かったから変えたわけじゃないです。でも、音を活かすかたちで、作画で芝居を変えたところはあります。地井さんが「姫~!」とか言って、チュッと口づけするところは、音を活かしてますね。
── あれは地井さんのアドリブなんですか。
西村:
ええ。平安時代の爺さんが口づけなんてするかどうか(笑)。あと、地井さんが「ひーめ! おいで!」と言っているとき、田辺さんはその声が泣いている声にも聴こえたらしいんです。だから、最初はムキになってやってるだけなんだけど、カットが変わると、いきなり泣き崩れてるじゃないですか。
── ええ、感極まって(笑)。
西村:
感極まったまま縁側から出ていって、姫を抱き上げて「わあ~、姫~! ん~、チュッチュ」ってやる。そこは作画で足しています。そういうアドリブを活かしていく力量が、アニメーターにも必要だった。田辺さんにはそういう力があったし、役者さんたちの芝居にも実感がこもってたから、コンテも進むようになった。冒頭30分のコンテを描くのに1年半かかりましたけど、残り4年半とか5年もかからずにすんだのは、やっぱりプレスコの効果でしょうね。
 |
ジ・アート・オブ かぐや姫の物語 鉛筆と水彩で描かれた映画のアートワークを紹介。 監督:高畑勲、人物造形と作画設計:田辺修、美術:男鹿和雄による解説も収録。 |