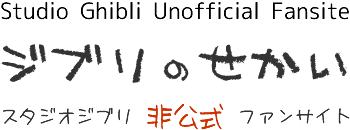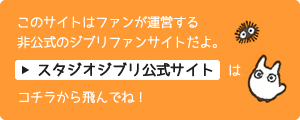『かぐや姫の物語』が、9月にトロント国際映画祭で上映されました。高畑勲監督も出席し、上映前の舞台挨拶に登場。上映後は、高畑監督のインタビューが行われました。これも通常より長く、熱心なやりとりとなり、10月の北米公開に向けて弾みがついたのではないでしょうか。
『かぐや姫の物語』が、9月にトロント国際映画祭で上映されました。高畑勲監督も出席し、上映前の舞台挨拶に登場。上映後は、高畑監督のインタビューが行われました。これも通常より長く、熱心なやりとりとなり、10月の北米公開に向けて弾みがついたのではないでしょうか。
人に訴える力のある絵で、映画を作りたかった
――かなり長いプロジェクトでしたが、これでこの旅も終わりという感じですか?
高畑:
そうですね。もう、忘れようと思ってるところです。
――この映画は、非常に完結されていて、綺麗な線で描かれてますけど、ここまでの美しさとシンプルさは一生かけて到達するものですか?
高畑:
いや、それは、一生かどうかは分からないけれど、ずっと前からの願いですね。セルアニメーションっていうのをずっとやってるんですね。もっと、人の心に直接訴えるような絵で表現したいって気持ちが、強くあったんですけど、なかなかそうもいかないわけですね。
実際、アメリカなんかはセルアニメーションって、ほとんど無くなって、その代りに立体的なものになってますね。それも一つの方法であると。そうじゃなくて、手で描くということの良さをもっと出したい、それをやっと実現したということですね。
――この映画の中には、スチールフレームもありますね。写真というか、動かないような場面もありますので、そういうのは他のアニメーション映画では、あまり見ないものだと思います。
高畑:
そうですかね。あまり、それは意識してないですけど。絵としての力があるというか、人に訴える力を持っている絵で、映画を作りたいと思ったことは確かです。
――いろいろな作品を作られる間に、技術、テクノロジーというものは、作品とか意図を示すための障害になるようなものになっていますか?
高畑:
うーん、ちょっと分からないんだけど。ぼくは、表現したいことがあって、表現したいことを表現できる技術の開発には、非常に熱心だったつもりなんですね。ただ、『かぐや姫』のようなものをやろうと思ったときには、それが描ける人、そういうタレントを持った、非常に優れた絵描きに恵まれる必要がある。で、自分としては今回恵まれて、それが完成したんだと思ってます。
――そういう描ける人を探すというのは、難しくなっていますか?
高畑:
一緒に仕事をしてきた人のなかに、そういう非常に優れた才能があることを、こちらとしては見出して、今までにやっていなかったことをやってもらう。で、本人たちも、それをやりたいと思って、それが合致したときに可能なんじゃないかと思ってます。
――彼たちにとっては非常にやりたいというか、普通の仕事と違うリフレッシュできるような作業だったと思いますけど。
高畑:
そう思いますね。
ぼくは作家というより演出家
――50年程、アニメーションに携わってらっしゃいますが、何がその道に入るインスピレーションでしたか? 何か特定の映画を観たとか、絵を描くのが好きだったとか、そういうことでしょうか?
高畑:
特定の映画を観た、ということですね。その映画というのは、フランスのアニメーション映画だったんですけど、題名をどう言えばいいのかな。フランスでは「La Bergere et le Ramoneur(『王と鳥』)」っていうんですけど。
そんなに大きくヒットしたわけじゃないし、外国では公開の仕方も大きくは取り上げられなかったんですけど、ぼくとしてはビックリしたんです、その作品を観て。アニメーションって、こんな凄い表現ができるのかって。それで、この道に近づいたわけです。
実際、自分が作ってる作品というのは、その作品とは違うんですけど。でも、アニメーションがこんな凄い表現を持ってるってことについて、気づかせてくれたことが凄く大きかったですね。
――作品を作るということの芸術的な面が、非常に楽しかったのですか? それとも、作るというプロセスが良かったんですか? また、プロセスに慣れたり、楽しむのには時間が掛かりましたか?
高畑:
プロセスもたいへん好きですね。っていうのは、協力して作っていくわけですね。そういうタレントを持った、絵描きの人たちと一緒に。仕事を作りあげていくわけですから、その過程そのものをたいへん楽しみながらというか、苦労はするものの同時に楽しみも感じながらやってました。
ぼくは、作家というより、やっぱり、演出家だと自分のことを思ってるんですね。だから、いろんなことをやってきました。原作のあるものとか、様々なものを、如何に面白い表現に達するかっていうことをやってた人間ですからね。先に言ったように、プロセスそのものを楽しみながらやってきました。
――じゃあ、監督をなさるときは、ちょっと違うような感じでなさるんですか?
高畑:
違うというのは?
――プロデューサーとかそういうことをやられたり。
高畑:
いやいや、監督とは演出。ディレクター=演出。私のいま言おうとしたことは、ディレクターっていうのは――プロデューサーは別で、ディレクターとして作品を作るときというのは、非常に面白いわけなんですけど。自分は絵を描かないかもしれないけど、どう描くかということに非常に深い、細かいところまで立ち入ってやるっていうのかな。その工夫が活きてくるっていう。いちばん大事なところは、才能を持っている絵描きでも、そういうことをやろうと思ってなかった人に、こうやったら面白いんじゃないかということを提案して、それで描いてもらって、それをチェックして、さらに良いものにしていくっていう、その過程が非常に楽しいということなんですね。
観客が、能動的に想像力を使える映画にしたかった
――『かぐや姫の物語』に関しては、どうのようなテーマを出したいか、もしくは表現方法などは、はっきりしたアイディアがあったんですか? また、それをアニメーターに何回も伝えることが出来ましたか?
高畑:
今度の作品は、こういう表現をしたいという、表現そのものが先に決まっていたっていうか。他の内容のものを作る場合でも、こういう表現をしたと思うんですね。ですから、別の問題として言うんですけど、今度の作品は、日本でいちばん古い物語で――神話はもっと古いのがありますけど――これは十世紀に書かれたんですけど、日本人なら全員が知ってるようなものを取り上げながら、観た人が「『かぐや姫』の話というのは、こんな話だったのか」ってビックリし、新鮮なものとして受け止めることの出来るようなものにしたいと思ったんですね。ひとつのアイディアに基づいています。
――ひとつのものを、出来るだけ少なく描くということですか? 顔の表情とか、いろいろなディテールを省いたり。それと、非常に美しく、流れるような線があるんですけど、そういう表現を目指してらしたんですか?
高畑:
表情とか、それから動物とか子どもたちの動きとか、そういうものについては全然、省くつもりはなくて。日本で普通にやっているアニメーションに比べて、もっと表現が多いんじゃないかと思ってます。
ただ、仰った、省くほうは、人の想像力をいきいきとかき立てることを主眼にしているからなんですよ。「こうなんですよ」って観客に押し付けるんじゃなくて、観客のほうがむしろ能動的に、観客の人が自分たちで想像力を使って、実感を受け止めるというか、本当らしい感じを受け止めることができる、そういうことを目指したんです。
――ひとつのシークエンスなんですけど、父親の顔が変化するときにディテールが出て、またそれがなくなるというような、フォーカスじゃないですけど、芸術的な選択として使われたようなやり方だったと思います。非常に美しかったです。
陰影のついた3DCGは、観客の想像力が衰える
高畑:
今の映画というのは、自分が提示してるのがほんものだって言い過ぎてるんですね。さっき、ちょっと言いましたけど、3DCGっていう立体的なものになってるのは、陰影が付きすべてが立体感をもって動き始めると、そのために失ったものが、もの凄く大きいと思うんですよ。そういうことをすると、観客の想像力の発揮が衰える。それに対して、もっと能動的に映画の中に入ってきてもらって、受け取ってもらいたいというのが、この映画の狙いなんですね。
――こういう作品を作るのは、3DCGと同じくらい複雑性があると思いますけれど、ただ狙いが違うということになりますね。
高畑:
その通りです。コンピュータそのものは、非常にたくさん使ってるんですね。
これからは、新しい人たちが、別のことを始めなくちゃいけない
――これだけ長い期間やってらして、多くの作品を作られて、まだ今でも緊張されますか?
高畑:
そりゃそうですね。どう受け止めてもらうかとか、非常にドキドキしますよ。
――スタジオジブリを創立されたときに、これほど有名になって、アニメーションの頂点に立つという、そのような会社になることは、期待のなかにありましたか?
高畑:
いや、全然ありませんでした。なかったし、いつ潰れても良いんじゃないか、ということで出発してましたからね。
――では、楽になったという気はしますか?
高畑:
今ですか? うーん、そうですねぇ……。でも、こういう仕事って、やっぱり、ある時期っていうのが、あるんじゃないでしょうかねぇ。だから、宮崎が引退するとか言い出したように、集中して作品を生み出す時期っていうのがあってですね。また今度は、新しい人たちが、別のことをやらなくちゃいけないんじゃないですかね。そういう転換期に、差し掛かってるんじゃないかと思います。
――引退はなさるんですか?
高畑:
引退とかは言いません。それは、やれるんだったらやりたいと思いますけど、いろいろな条件があって、自分の体力や、頭もどうなるやら分からないし、それからお金もいっぱい掛かるから、実現は難しいと思ってるんですけど。出来ても良いし、出来なくても良いし、っていう感じなんです。
――実写映画の監督は、いちばん先に脚がダメになってしまうんですけど、アニメーション監督は何がいちばん先にダメになってしまうんでしょうか?
高畑:
頭じゃないでしょうかね。ぼくは、脚の話で言えば、遊びたいんですよ、自分がね。アニメーション映画を作る以外に本も書いたし、いろいろやってるんで。そのときに言ったんですよ、「いろんなところへ、行けるときに行かなくちゃ」って。で、「アニメーション映画は、車椅子でも作れるから」って言ってたんです。まあ、冗談ですけど(笑)。
長く観てもらえる映画になってほしい
――映画の反響に、監督の喜びはどの程度ありますか? 映画を作って、自分が納得して、自分が好きな映画が出来上がったっていうところで、非常に嬉しさがあると思うんですけど、日本とかアメリカとか、そういうところで、どういうふうに映画が受け止められるかっていうことも、ひとつの楽しみだと思いますが。
高畑:
若いときは、自分及びその仲間と、これだけのことをやったっていう、やったことに対する自信も含めて、それで満足してたんですね。でも、最近はやっぱり、どう受け止めてもらうかっていうことが、大事になってきました。実際、この映画に関して言うと、日本では観た人の数は、もの凄いヒットというわけではなかったかもしれないけれど、満足度が非常に高かったんで嬉しかったですね。
それでいうと、北米より前に、フランスで封切ったんです。フランスでも非常に満足度の高いものがあってですね、たいへん嬉しく思ってます。だから、カナダでも、アメリカ合衆国でも、そういう状態になってほしいなって、今思ってます。
――現在では、DVDやストリーミングなどで、映画を観ることができるんですけど、この映画は非常に長期的に、永遠に観られる映画だと思います。それは、お考えのうえで、作られてるんですか? 劇場だけじゃなく、テレビとかの画面で観てもらうということに対しては、どういう思いですか?
高畑:
もちろん、映画を作っていると、映画館の大きなスクリーンで観てもらいたいっていうのが、第一なんですけど。それ以外の形でも、観てもらえるのは嬉しいことです。それから、ずっとっていうのは、さっきの質問とも関係があるんですけど、テレビで放映されたときに、凄い低い視聴率のものがあったんですね。『ルパン三世』っていうんですけど。最初のシリーズですけどね。でも、それって、後になったら凄い人気が高まったんですよ。
そういうことで、先ほどお話したように、自分で仲間と一緒に、これは面白いんじゃないかと思って作ったものが、そうは外れてなかったんですね、その経過では。だんだん、みんな喜んでくれるようになって、生き残っていくってことがあったんで。今度の映画も、そうなってほしいし、そのためには別の形で、映画館だけじゃない形で、観てもらえるようになってほしいと思います。
――ご自分の映画が間違いじゃなかったって仰ったんですけど、私たちは間違ってるとは全然思っていません(笑)。
高畑:
長いことやっていると、いろんな浮き沈みがあったわけです(笑)。
――45年前と、今と比べて、上手くいったという一瞬は、昔も今も変わらなく楽しめますか?
高畑:
それは、その通りです。ただ、50年前と今では、まるで違うと思いますね。実は、50年よりもっと前なんですね、この道に入ったのは。1959年だから、もう55年間やってるわけです。
自分が、この道に入ったころに、日本ではもちろんのこと、世界的にもですね、こんなに人気が高まるとは全然思ってなかったです。非常に、運が良かったと思います。この道に入ったことが、幸運だったと思ってます。
――私たちも非常に幸運です。