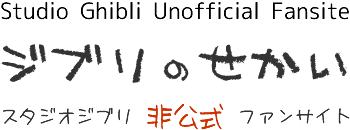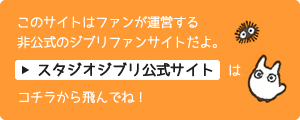9月6日、宮崎駿監督の引退記者会見が行なわれました。
今回の会見はニコニコ生放送を初めとして、テレビ局が70社、新聞・雑誌・ウェブメディアが200媒体。総勢605名の人たちが集まったそうです。質疑応答の形式で、終始和やかな引退会見となりました。当方も、必死に全文文字起こししたので、ご覧ください。
心にトゲが刺さっているのは『ハウル』というのが印象的でした。
文化人扱いされるのを嫌がり、町工場のオヤジなんだと言いはるのは宮崎監督らしいですね。
宮崎駿監督が報道陣に配布した「公式引退の辞」
ぼくは、あと10年は仕事をしたいと考えています。自宅と仕事場を自分で運転して往復できる間は、仕事をつづけたいのです。その目安を一応“あと10年”としました。
もっと短くなるかもしれませんが、それは寿命が決めることなので、あくまでも目安の10年です。
ぼくは長編アニメーションを作りたいと願い、作って来た人間ですが、作品と作品の間がずんずん開いていくのをどうすることもできませんでした。要するにノロマになっていくばかりでした。
“風立ちぬ”は前作から5年かかっています。次は6年か、7年か……それではスタジオがもちませんし、ぼくの70代は、というより持ち時間は使い果たされてしまいます。
長編アニメーションではなくとも、やってみたいことや試したいことがいろいろあります。やらなければと思っていること--例えばジブリ美術館の展示--も課題は山ほどあります。
これ等は、ほとんどがやってもやらなくてもスタジオに迷惑のかかることではないのです。ただ家族には今までと同じような迷惑をかけることにはなりますが。
それで、スタジオジブリのプログラムから、ぼくをはずしてもらうことにしました。
ぼくは自由です。といって、日常の生活は少しも変わらず、毎日同じ道をかようでしょう。土曜日を休めるようになるのが夢ですが、そうなるかどうかは、まぁ、やってみないと判りません。
ありがとうございました。
宮崎駿 長編アニメーション引退会見
――引退報道を受けて、ファンの子供たちから感謝や「やめないで」という声が届いております。監督から、子供たちへメッセージをいただけますか。
宮崎:
そんなにかっこいいことは言えません。なにかの機会があったら、私たちが作った映画を観てくだされば、何か伝わってくれるかもしれません。それに留めさせてください。
――引退の辞を読ませていただきました。「長編映画」の引退という解釈でよろしいでしょうか? また、今後の活動を教えてください。
宮崎:
この辞を、我ながらよく書いたなと思ったんですけど、「僕は自由です」と書いてありますから、やらない自由もあるんです。
ただ、車が運転できる限りは、毎日アトリエに行こうと思っています。
それで、やりたくなったものや、やれるものはやろうと思っています。
まだ休息を取らなければいけない時期なので、休んでるうちに分かってくるだろうと思うんですが、ここで約束すると、たいてい破ることになると思いますので。そういうことで、どうかご理解ください。
――『風の谷のナウシカ』の続編を作る予定はありますか?
宮崎:
それはありません。
――韓国にも宮崎駿監督のファンがたくさんいます。私もその一人です。韓国のファンに一言お願いします。それから、今話題になっている零戦について、どんなお考えかお願いします。
宮崎:
映画を観ていただければ、分かると思っていますので、いろんな言葉に騙されないで、今度の映画も観ていただけたらいいなと思います。
いろんな国の方々、私たちの作品を観てくれて、非常に嬉しいと思っています。
それと同時に、『風立ちぬ』のモチーフそのものが、日本の軍国主義が破滅に向かっていく時代を舞台にしていますので、いろいろな疑問や――私の家族からも、スタッフからも出ました――それにどういうふうに答えるかということで、映画を作りました。
ですから、映画を観ていただければ分かると思います。映画を観ないで論じても、始まらないと思いますので、是非お金を払って観ていただけると嬉しいなと思います。
――今後、ジブリの若手監督の監修やアドバイザーなどの関与はありますか?
宮崎:
ありません。
――「今回の引退は本気です」ということですが、今回と今までは何が違うのかお聞かせください。
宮崎:
「公式引退の辞」に書いてありますけど、『風立ちぬ』は『ポニョ』から5年かかってるんです。
もちろんその間、映画を作り続けていたわけではなく、シナリオを書いたり道楽の漫画を描いたり、あるいは美術館の短編をやるとか、いろんなことをやっていますが、やはり5年かかるんです。
今、次の作品を考えますと、5年じゃ済まないでしょうね、この年齢ですから。そうすると、次は6年かかるか7年かかるか。
あと三月もすればですね、私は73歳になりますから、それから7年かかると80歳になってしまうんです。
このまえお会いした、半藤一利さんとお話してですね、その方は83歳でしたが、ほんとうに背筋が伸びて、頭もはっきりしていてですね、ほんとうにいい先輩がいるって。ぼくは83歳になって、こうなってたらいいなと思うもんですから、あと10年は仕事を続けますと言ってるだけでして。
続けられたら良いなと思いますが、今までの延長上には、自分の仕事は無いだろうと思っています。
そういうことで、ぼくの長編アニメーションの時代は、はっきり終わったんだって。
もし、自分がやりたいと思っても、それは年寄りの世迷い言である、っていうふうに片付けようと決めています。
――引退を正式に決めたタイミングと、鈴木さんとどのような会話をしたか教えてください。
宮崎:
よく覚えてないんですけど、「鈴木さん、ぼくはもう駄目だ」と言ったことはあります。それで、鈴木さんが「そうですか」って。
それは、何度もやってきたことなんで、そのときに鈴木さんが信用したかどうかは分かりませんが。
ジブリを立ち上げたときに、こんなに長く続ける気がなかったことは確かです。
ですから、何度も、もう引きどきなんじゃないかとか、辞めようという話は、ふたりでやってきましたので。
今回は、ほんとうに次は7年かかるかもしれないと、鈴木さんもリアリティを感じたんだと思います。
鈴木:
ぼくも正確に覚えているわけじゃないんですけども、『風立ちぬ』の初号があったのが6月19日なんですよ。
たぶん、その直後だったんじゃないかと思うんですよね。
それで、そういう話があったとき、確かにこれまでもいろんな作品で、「これが最後だ」「これが最後だと思ってやっている」っていろんな言い方あったんですけどね、そのときの具体的な言葉は忘れましたけど。
今回は、本気だなっていうことを、ぼくも感じざるを得ませんでした。
というのは、ぼく自身がですね、『ナウシカ』の製作を始めてから数えると、今年がちょうど30年目にあたるんですけどね、その間ほんとうにいろいろありました。
ジブリを続けていく間にですね、宮さんも言ったように、これ以上やるのはよくないんじゃないか、やめようか、やめまいかとか、いろんな話があったんですけどね。
それまでの30年間、緊張の糸っていうのは、ずーっとあったと思うんですよ。その緊張の糸がですね、宮さんにそのことを言われたとき、少し揺れたんですよね。
変な言い方をすると、ぼく自身が少しホッとするところがあったんですよ。
だから、若いときだったら、それを留めさせようとか、いろんな気持ちも働いたと思うんですけど。
自分の気持ちのなかで、括弧付きなんですけど、ほんとうに「ご苦労様でした」という気分が湧いた? そういうこともあるような気がするんですよね。
ただ、ぼく自身は、なにしろ今引き続いて『かぐや姫』っていう映画を公開しなきゃいけないんで、その途切れかかった糸を、もう1回縛ったりしてね、現在仕事をしている最中なんですけど。
それで、実はですね、それを皆さんにお伝えするまえに、いつ皆さんの方にそれをお伝えしようかってことを話し合いました。
皆さんにお伝えするまえに、まずそれを言わなきゃいけないのは、スタジオで働くスタッフに対してだと思ったんですよ。それをいつやって、それで皆さんにいつ伝えるか。
それで『風立ちぬ』の公開がありましたからね、映画の公開前に、映画が出来てすぐ引退なんてことを発表したら、これは話がややこしくなると思ったんですよ。
だから、映画の公開をして、落ち着いた時期、実は社内ではですね、8月の5日にみんなに伝えることをしました。
そして、映画の公開が一段落した時期、そのときに皆さんにも発表できるかなと。
それで、いろいろ考えたんですけれど、そうなると時期は9月の頭ですよね。そんなふうに考えたことは確かです。
――台湾の旅行者は、日本に行くとジブリ美術館は外せない観光名所となっています。引退後は海外旅行をかねて、ファンと交流する予定はありますか?
宮崎:
ジブリ美術館の展示その他については、私は関わらせてもらいたいと思ってますので、ボランティアの形になるのかもしれませんが――自分も展示品になっちゃうかもしれませんので(笑)、是非、美術館の方にお越しいただいたほうが嬉しいんです。
――鈴木さんに質問です。『風立ちぬ』で最後になる予感はありましたか?『ポニョ』で終わらせたくないという思いはなかったのでしょうか? 宮崎監督には引き際の美学がありましたお聞かせください。
鈴木:
『風立ちぬ』っていう作品が最後になる予感はあったのかっていう、そういうご質問だと思います。
ぼくはですね、宮さんと付き合ってきて、彼の性格からしてですね、ひとつ思ってたことは、ずっと作り続けるんじゃないかなって、そう思ってました。
ずっと作り続けるっていうのは、どういうことかと言ったら、死んでしまうまで、その間際まで作り続けるんじゃないかって。
まあ、すべてをやるってことは不可能かもしれないけど、何らかの形で映画を作り続ける。という予感の一方で、宮さんという人はですね、ぼくが35年付き合ってきて、常々感じてたんですけど、何か別のことをやろうっていうときに、自分で一旦決めて、それをみんなに宣言をするって人なんですよ。
もしかしたら、これを最後に、それを決めて、宣言して、それで別のことに取り掛かる。そのどっちかだろうって、正直いうと思ってましたね。
それで『風立ちぬ』って作品を作っていって、完成を迎え。その直後に、さっき言ったようなお話が出てきたんですけど。
そうすると、それはですね、ぼくの予想のなかに入ってましたよね。だから、素直に受け止めることができたっていうんですかね。
宮崎:
映画を作るのに死に物狂いで、その後どうするかは考えていなかったです。
それよりも、映画が出来るのか、っていう。これは映画になるのかとか、作るに値するものなのかとか、そういうことが自分にとっては重圧でした。
――宮崎監督はノルシュテインから影響を受けたとお聞きしましたが、どのような影響を受けたか教えてください。
宮崎:
ノルシュテインは友人です。「負けてたまるか」という相手でございまして(笑)。
彼は、ずっと『外套』を作っていますね。ああいう生き方も、ひとつの生き方だと思います。
今日、実はここに高畑監督も出ないかって誘ったんですけど、「冗談ではない」という顔をして断れまして、彼はずっとやる気だなと思っています。
――これまで作ってきた作品で最も思い入れのある作品は? すべての作品において、こういうメッセージを入れようというのはありますか?
宮崎:
いちばん自分のなかに、棘のように残っているのは『ハウルの動く城』です。
ゲームの世界なんです。でも、それをゲームではなくドラマにしようとした結果――ほんとうに格闘しましたが、スタートが間違ってたと思うんですけど、自分が立てた企画だから仕方がありません。
それで、ぼくは児童文学の多くの作品に影響を受けて、この世界に入った人間ですので。
今は児童書にもいろいろありますけど、基本的に子どもたちに「この世は生きるに値するんだ」っていうことを伝えるのが、自分たちの仕事の根幹になければいけないと思ってきました。それは、今も変わっていません。
――イタリアを舞台にした作品をお作りですが、イタリアは好きですか? 半藤さんは83歳でご立派ですが、日野原先生を目標にされたほうが、あと30年生きられるのでいいと思います。あとジブリ美術館で館長をされると、ファンは喜ぶと思います。
宮崎:
イタリアは好きです。まとまっていないとこも含めて好きです。それから、友人もいるし、食べ物は美味しいし、女性は綺麗だし。でも、ちょっとおっかないかなという気もしますが、イタリアは好きです。
それから、半藤さんとのころに10年経てばたどり着けるのかっていう、その間仕事を続けられたらいいなと思っているだけで、それ以上望むのはちょっと。
半藤さんが、あと何年頑張ってくださるか分かりませんから。半藤さんは、ぼくより10年間前を歩いているんで、半藤さんはずっと歩いていてほしいと思ってます。
それから、館長になって入口で「いらっしゃいませ」っていうよりは、展示の物が10年以上前に描いたものなので、ずいぶん色あせていたり、描き直さなければいけないものがありまして、それをぼくはやりたいと思ってるんです。
これは、自分が筆で描いたり、ペンで描いたりしなければいけないものなんで。
これは是非、時間があったらやらなければいけないと思っていたことなんで、それをやりたいんです。
美術館の展示品っていうのは、毎日掃除してきちんとしてるはずなのに、いつのまにか色あせてくるんですよね。
その部屋に入ったときに、全体がくすんで見えるんです。そのくすんで見えるところを一箇所、なにかキラキラさせると、そのコーナーがパッとよみがえって、不思議なことに、たちまちそこに子供たちが群がるということが分かったんです。
ですから、美術館をいきいきさせていくには、ずっと手を掛け続けなければいけないということは確かなので、それを出来るだけやりたいと思っています。
――長編アニメーションを引退されるということですが、美術館の短編に関わることは? それとジブリの今後はどうなるか、鈴木さんにお伺いしたいです。
宮崎:
「引退の辞」に書きましたように、ぼくは自由です。やってもやらなくても自由なので、今そちらに頭を使うことはしません。
まえからやりたかったことがあるので、そっちをやろうと。とりあえず。
それはアニメーションではありません。
鈴木:
ジブリはこれからどうするんだ、というご質問だと思うんですけど。
ぼくは、今現在、繰り返しますけど、『かぐや姫』のあと、来年の企画に係わっています。
それで、ぼくもですね、年齢が宮さんよりけっこう若いんですけど、現状65歳でありまして。
それで、このジジイがですね、いったいどこまで係わるのかという問題があるんですけどね、このジブリの問題というのは、今ジブリに居る人の問題でもあると思うんですよ。
だから、その人たちがどう考えるのか。そのことによって決まるんだと思っています。
宮崎:
ジブリの今後についてはですね、やっと上の重石がなくなるんだから、「こういうものやらせろ」っていう声がですね、若いスタッフからいろいろ鈴木さんに届くことを、ぼくは願ってますけどね。ほんとうに。
それがないときは駄目ですよね、鈴木さんが何をやっても。
それで、ぼくらは30のときも40のときも、やっていいんだったらなんでもやるぞ、っていろんな企画を抱えていましたけれど、それを持っているかどうかにかかっていると思います。門前払いを食わす人ではありません、鈴木さんは。
そういうことで、今後のことは、いろんな人間の意欲や、希望や、能力にかかっているんだと思います。
――『風立ちぬ』が最後の長編になりましたが、他にこれはやってみたかったという長編作品があったら教えてください。
宮崎:
それは、ほんとうに山ほどあるんですけど、やってはいけない理由があったからやらなかったことなので、今ここで述べようもない、それほどの形にはなってないものばかりです。
やめると言いながら、こういうのをやったらどうなんだろう、ということはしょっちゅう頭に出たり入ったりしますけど、それは人に語るものではありませんので、ご勘弁ください。
――具体的に今後の活動を教えてください。これから違う形で、いろんなことを発信していくことがありますか?
宮崎:
やりたいことがあるんですけど、やれなかったらみっともないので、何だか言いません。
それから、ぼくは文化人になりたくないんです。ぼくは町工場のオヤジです。それは貫こうと思っているので、発信しようとか、あまりそういうことを考えないです。
文化人ではありません。
――当面は休息するという認識で良いのでしょうか? また、東日本大震災や原発が『風立ちぬ』に与えた影響を教えてください。
宮崎:
『風立ちぬ』の構想は、震災や原発に影響されていません。それはこの映画を始めるときに、初めからあったものです。
どっかで話しましたけど、時代に追いつかれて、追い抜かれたという感じを、映画を作りながら思いました。
それから、休息ということはですね、ぼくの休息は、他人から見ると休息に見えないような休息でして。
仕事を好き勝手にやっていると、大変でも休息になるということはあるんで。ただ、ごろっと寝っ転がっていると、かえってくたびれるだけなんで。
夢としては、出来ないと思いますけど、東山道を歩いて、京都まで歩けたらいいなと思ったりするんですけど、途中で行き倒れになる可能性のほうが強いです。それはときどき夢見ますけど、たぶん実現不可能だと思います。
――時代に追いつかれ追い抜かれたということですけど、それと引退は関係あるのでしょうか?
宮崎:
関係ありません。
アニメーションの監督は、何をやっているのかっていうのは、皆さんよく分からないことだと思うんですけど。
アニメーションの監督といっても、みんなそれぞれやり方は違います。ぼくはアニメーター出身なもので、描かなきゃいけないんです。描かないと表現できないんで。そうすると、どういうことが起こるかといいますと、メガネを外してですね、こうやって(突っ伏して)描かなきゃいけないんです。
これを延々とやってかなきゃいけないんですけど、どんなに体調を整えて、節制していても、それを集中していく時間が年々減っていくことは確実なんです。もう、それを実感しています。
それで、『ポニョ』のときに比べると、ぼくは机を離れるのが30分早くなっています。この次は、さらに1時間早くなるんだろうと。
その物理的な加齢によって発生する問題は、どうすることも出来ませんし、それでイラだっても仕方がないんですね。
では、違うやり方をすればいいじゃないか、という意見があると思いますが、それが出来るならとっくにやっていますから、出来ません。
というわけで、ぼくはぼくのやり方で、一代を貫くしかないと思いますので、長編アニメーションは無理だという判断をしたんです。
――今、自称クールジャパンとして見られる日本のアニメがあります。宮崎監督はどのように見ていますか?
宮崎:
まことに申し訳ないんですが、わたしが仕事をやるということは、一切映画も見ないテレビも見ないという生活をすることです。
ラジオだけは、朝ちょっと聴きます。新聞は、ぱらぱらっと見ますが、あとはまったく見てません。驚くほど見てないんです。
だから、ジャパニメーションっていうのが、どこにあるのかすら分かりません。ほんとうに分からないんです。
予断で話すわけにいきませんから、それに対する発言権は、ぼくにはないと思います。
皆さんも、わたしの年齢になって、わたしと同じデスクワークをやっていたら分かると思いますが、そういう気を散らすことは一切出来ないんです。
参考試写という形で、スタジオの映写室で何本か映画をやってくださるんですけど、たいてい途中で出てきます。仕事をやったほうが良いと思って。
そういう不遜な人間なんで、今が潮だなと思います。
――引退宣言をしないで引く監督もいますが、あえて引退宣言をされようと思った理由は?
宮崎:
引退宣言をしようって思ったんじゃないんです。ぼくは、スタッフに「もう辞めます」って言いました。その結果、プロデューサーのほうからですね、それに関していろんな取材があるけど、どうするかって。いちいち受けていたら大変ですよ、っていう話がありまして。「じゃあ、ぼくのアトリエでやりましょうか」っていう申し入れをしたらですね、ちょっと人数が多くて入りきれないって話になりまして。じゃあ、スタジオの5スタというところに会議室がありますので、そこでやりましょうかって言ったら、そこも難しいって話になって、ここになっちゃったんです。
そうするとですね、これは何かがないと、口先だけで誤魔化しているわけにいかないんで、「公式引退の辞」っていうのを書いたんです。
それをプロデューサーに見せたら、「これいいじゃない」って言うんで、「これコピーしてください」って。それで、こういうことになりました。
こんなイベントをやる気は、さらさらなかったんです。
――宮崎作品は商業的成功と芸術性の評価の両方納めましたけど、宮崎作品のスタイルをプロデューサーの言葉で表現していただければと思います。そして、宮崎映画が日本映画界に及ぼした影響を解説いただければ。
鈴木:
これいい訳かもしれないんですけど、そういうことあまり考えないようにしているんですよね、ぼく。
それで、どうしてかっていうと、そういうふうにものを見ていくと、目の前の仕事が出来なるなるんですよ。だから、ぼくなんかは、現実には、宮崎作品に関わったのはナウシカからなんですけどね、そこから約30年間、ずっと走り続けてきて、それと同時にですね、過去の作品をやっぱり振り返ったことがなかったんですよ。
それが多分、仕事を現役で続けるってことだとぼくは思ってたんですよね。だから、どういうスタイルでその映画を作っているのか、ふと自分の感想として思うことはありますけど、なるたけそういうことは封じる? なおかつ、自分たちが関わって作ってきた作品が世間にどういう影響を与えたか、それもですね、ぼくは実はあまり考えないようにしていました。これがお答えになるかどうか、そういうことです。
宮崎:
ええ、まったく、ぼくも考えてませんでした。あの、採算分岐点にたどりついたって聞いたら「よかった!」って、それでだいたい終わりです。
――さきほどイタリアが好きだという話がありましたけど、フランスはいかがでしょうか?
宮崎:
あの、正直に言いますね。イタリア料理の方が口に合います(笑)。クリスマスにたまたまフランスにちょっと用事があって行ったときにですね、どこのレストランに入ってもフォアグラが出てくるんです。これは辛かったなという記憶があるんですけど。
それは答えになってませんか? ああ、ルーブルは良かったですよ。いいところはいっぱいあります。ありますけど、料理はイタリアの方が好きだっていう。あの、そんな、たいした問題と思わないでください(笑)。
フランスの友人に、「イタリアの飛行艇じゃなくてフランスの飛行艇の映画を作れ」って言われたんですけど、アドリア海で飛んでたからフランスの飛行艇はないだろうと、そういう話をした記憶がありますけど。
フランスは、ポール・グリモーという人がですね、「王と鳥」という名前になっていますが、昔は「やぶにらみの暴君」というかたちで、完成形ではなかったけれども、日本で1950年代にに公開されてですね、甚大な影響を与えたんです。特に、僕よりも5つ先輩の高畑監督の世代には圧倒的な影響を与えた作品です。ポール・グリモーって人は。それは、ぼくらは少しも忘れていません。今見てもその志とか、その世界の作り方については本当に感動します。
いくつかの作品がきっかけになって、自分はアニメーターをやっていこうというふうに決めたわけですから、そのときにフランスで作られた映画の方がはるかに大きな影響を与えています。で、イタリアで作られた作品もあるんですけども、それを見てアニメーションをやろうと思ったわけではありません(笑)。
――1963年の東映動画入社されて半世紀を振り返って一番つらかったこと、アニメ作っていてよかったことを教えてください。
宮崎:
つらかったのは本当にスケジュールで、どの作品もつらかったです。それから、終わりまで分かっている作品は作ったことがないんです。つまり、こうやって映画が収まっていくというふうな、見通しがないまま入る作品ばっかりだったので、それは毎回ものすごく辛かったです。つらかったとしか言いようがないですけど。それで、最後まで見通せる作品は、ぼくがやらなくていいと勝手に思い込んで、企画を立てたりシナリオを立てたりしました。
あの、絵コンテという作業があるんですけど、まるで新聞連載のように絵コンテを描いている――いや新聞連載ほどせっせとやってませんね、あの、月刊誌みたいな感じで絵コンテを出す。スタッフはこの映画がどこにたどりつくか全然分からないままやってるんです。よくまぁ、我慢してやってたなと思うんですが。そういうことが自分にとっては、いちばんしんどかったことです。
でも、その2年とか、1年半とかいう時間の間に考えることが、自分にとっては意味がありました。同時に、それでもあがってくるカットを見て、これはああではない、こうではないと自分でいじくってく過程で前よりも映画の内容についての自分の理解が深まるということも事実なんで、それによってその先が考えられるというふうな、あまり生産性には寄与しない方式でやりましたけど、それはつらいんですよね(笑)。
とぼとぼとスタジオにやって来るというふうな日々になってしまうんですが。50年のうちに何年そうだったかは分かりませんけど、そういう仕事でした。
――監督になってよかったと思ったことは?
宮崎:
監督になってよかったと思ったことは1度もありませんけど、アニメーターになってよかったと思ったことは何度かあります。
アニメーターというのは、本当に何でもないカットが描けたたとか、うまく風が描けたとか、うまく水の処理ができたとか、光の差し方がうまくいったとか、そういうことで2、3日は幸せになるんですよ。短くても2、3時間ぐらいは幸せになれるんです。
監督はね、なんか最後に判決を待たないといけないでしょ。これは、胃によくないんです。アニメーターを最後までやってたつもりでしたけど、アニメーターという職業は、ぼくは、自分に合っている、いい職業だったと思っています。
――それでも監督をずっとやって来られたのはどうしてでしょうか?
宮崎:
簡単な理由でして、高畑勲とぼくらは労働組合の事務所で出会って、ずいぶん長いこと話をしました。その結果、一緒に仕事をやるまでにどれほど話したかわからないぐらい、ありとあらゆることについて話をしてきました。それで、最初に組んでやった仕事は、いま話をしても仕方がありませんけど、自分がそれなりの力を持って彼と一緒にできたのは『ハイジ』が最初だったと思うんですけど、そのときに、まったく打ち合わせが必要のない人間になっていたんです、相互に。こういうものをやる、と出したとたんに、何を考えているか分かるという人間になっちゃったんです。
ですから、監督というのは、スケジュールが遅れると会社に呼び出されて怒られる。高畑勲は始末書をいくらでも書いてましたけど、そういうのを見るにつけ、ぼくは監督はやりたくない、やる必要はない、ぼくは映像のほうをやってればいいんだ、というふうに思っていました。ましてや音楽は何やらかにやらというのは全然、修行もしなければ何もやらない、そういう人間でしたから。
ある時期がきて、「おまえ1人で演出をやれ」と言われたときは、ほんとうに途方に暮れたんです。音楽家との打ち合わせなんて言われても、何を打ち合わせしていいか分からない、よろしくと言うしかない。しかも、さっき言いましたように、「このストーリーがその後、どうなっていくんですか」と聞かれても「ぼくもわかりません」と言うしかないんで。
つまり、初めからまったく監督や演出をやろうとした人間じゃなかったんです。それがやったので、途中パクさんに助けてもらったこともありますけど、その戸惑いは『風立ちぬ』までずっと引きずってやってきたと、今でもぼくは思っていますけどね。
音楽の打ち合わせで「これどうですか」と聞かれても、「どっかで聞いたことあるな」とかそれぐらいのことしか思いつかないので。
逆に「このCD、ぼくとても気に入ってるんですけど、これでいけませんか」「これワーグナーじゃないですか」とか、そういうバカな話はいくらでもあるんですけど、本当にそういう意味では、映画の演出をやろうと思ってやってきたパクさんの修行と、絵を描けばいいんだと思っていたぼくの修行は全然違うものだったんです。
それで、監督をやっている間も、ぼくはアニメーターとしてやりましたので、多くの助けやとんちんかんがいっぱいあったと思うんですけど、それについてはプロデューサーがずいぶん補佐してくれました。つまりテレビも見ない、映画も見ない人間にとっては、どういうタレントいるとかそういうのは何も知らないんです。で、すぐ忘れるんです、ぼくは。
ですからこれはまあ、そういうチームというか、腐れ縁というか、そういうのがあったおかげでやれてこれたんだって、ほんとうに思います。決然と立って、1人で孤高を保っているとか、そういう監督では全然なかったです。わかんないものはわかんないという、そういう人間として最後までやれたんだと思います。
――高畑さんの『かぐや姫の物語』を少しはご覧になっていると思うんですけど。
宮崎:
いや、ぼくは全然見てません。今日、ここに一緒に並ぼうよとぼくは持ちかけたんですが、「いやいやいや」と。まだまだやる気だなと思っています。
――『風立ちぬ』で最後のセリフを「あなた来て」から「あなた生きて」に変えたということですが、変えたことについてどう思っていらっしゃるかお願いします。
宮崎:
『風立ちぬ』の最後については、ほんとうに煩悶しましたけど、なぜ煩悶したかっていったら、とにかく絵コンテを上げないと、製作デスクのサンキチが――三吉という女の子がいるんですけど、今は産休で休んでますが――、ほんとうに恐ろしいんです。他のスタッフのとこに行って話していると、床に「10分にしてください」とか貼ってあるとかね。机の中にいろんな叱咤激励が貼ってありまして。ま、そんなことはどうでもいいんですけど(笑)。
とにかく絵コンテが形にしないことにはどうにもならないので、いろいろペンディング事項があるけど、とにかく形にしようってことで、形にしたのが追い詰められた実態です。それで「やっぱりこれはダメだな」と思いながら、絵が描かれてもセリフは変えられますから、その時間に自分で、冷静になって仕切り直しをしたんです。
ぼくは、こんなことを話しても仕方ないんですけど、最後の草原はいったいどこなんだろう、これは煉獄であるというふうに仮説を立てたんですね。ということは、カプローニも堀越二郎もですね、もう亡くなってそこで再会しているんだというふうに、そういうふうに思ったんです。それで、菜穂子はベアトリーチェだ。だから「迷わないでこっちに来なさい」という役で出てくるんだってことを言い始めたら、自分でこんがらがりまして、それをやめたんですよね。やめました。やめたことによって、すっきりしたんだと思います。「神曲」なんか一生懸命読むからいけないんですよね。
――長編アニメで作りたい世界観が表現できたという達成感はありますか? もし悔いが残っているとしたらどのような部分なのでしょうか。
宮崎:
その総括はしてません。自分が手抜きしたというふうな感覚があったらつらいだろうと思うんですけど、とにかくたどり着ける所まではたどり着いた、というふうにいつでも思っていましたから、終わった後は、もうその映画は見ませんでした。駄目なところは分かっているし、いつの間にか直っているとか、そういうことも絶対にないんで、振り向かないように、振り向かないようにやっていました。
同じことはしないっていう。「同じことをいっぱいした」って言われてるんですけど、同じことはしないつもりでやってきたんです。
――スタジオジブリを立ち上げたのが40代半ばごろですが、今まで日本の社会はどう変わってきたとお感じになっているでしょうか。どんな70代にしたいとお考えでしょうか。
宮崎:
ジブリを作ったときの日本のことを思い出すとですね、浮かれ騒いでる時代だったと思いますよ。経済大国になって、日本はすごいんっていうふうにね、ジャパンイズナンバーワンとかね、そういうことを言われていた時代だと思うんです。
それについて、ぼくはかなり頭にきていました。頭にきてないと『ナウシカ』なんか作りません。でも『風の谷のナウシカ』、それから『ラピュタ』、『トトロ』、『魔女の宅急便』というのは、基本的に、経済は勝手ににぎやかだけど心の方はどうなんだとかね、そういうことをめぐって作っていたんです。
でも、1989年にソ連が崩壊して、それから日本のバブルもはじけていきます。その過程でですね、もう戦争は起こらないと思っていたユーゴスラビアがですね、すごい内戦状態になるとか、ほんとうに歴史が動き始めました。
で、今まで自分たちが作ってきた作品の延長上に、これは作れないという時期が来たんです。そのときに体をかわすようにですね、豚を主人公にしたり、高畑監督は狸を主人公にしたりして切り抜けた、切り抜けたなんていったら変ですけど多分そうです。
それから、長い下降期に入ったんです。失われた10年は失われた20年になり、半藤一利さんは失われた45年になるであろうと予言しています。多分そうなるんじゃないか。そうすると僕らのスタジオってのは、その経済の上り調子のところで、バブルが崩壊するところで引っかかってたんです。それがジブリのイメージをつくったんです。
その後、じたばたしながらですね『もののけ姫』を作ったり、いろいろやってきましたけど、ぼくの『風立ちぬ』まで、ずるずるずるずると下がりながら、これは一体どこへ行くんだろう?と思いつつ作った作品だと思います。ただ、このずるずるずるが長くなりすぎると、最初に引っかかってた『ナウシカ』以降の引っかかりが、もう持ちこたえられなくなって、どろっと行く可能性があるところまで来ているのではないかと。
抽象的な言い方で申し訳ありませんが、ぼくの70歳というのは、半藤一利さんとお話したときに、ほんとうによく分かったんですが、ずるずるずると落ちてくときに、自分の友人だけではなくて、若い一緒にやってきたスタッフや、隣の保育園にいる、子どもたちの生きているところを、自分は横にいるわけですから、なるべく背筋を伸ばして、半藤さんのように、きちんと生きなければいけないというふうに思ってますけど、そういうことだと思います。
――ジブリの作品は将来、中国で上映する予定はありますか?
星野:
ご存じの通り、中国は外国映画の上映に規制があり、その本数がだんだん規制緩和で、増えているとう状況はよく分かっているんですけども、またまだ、そういう面では本格的に日本の作品が上映していく流れっていうは、できていないんだと思います。前向きには考えてはいますけども、現時点ではジブリの作品は上映されている状況にはありません。
――宮崎監督が好きな作品や監督は?
宮崎:
さっきもお話したように、ぼくはいまの作品を全然みていないので、ノルシュテインは友人だ、ピクサーのジョン・ラセターは友人です。イギリスのアードマンにいる連中も友人です。みんなややこしいところで、苦闘していろいろやっているという意味で友人です。競争相手ではないと、ぼくはいつも思っているんですけど。それから、いまの映画、見てないんですよ、ほんとうに。申し訳ないんですけど、だから……すみません。
高畑監督の映画は観ることになると思いますが、まだ覗くのは失礼だから、覗かないようにしています。
――『風立ちぬ』では庵野秀明さんやスティーブン・アルパートさんなど監督とゆかりの深い方々が出演しています。そのキャスティングの裏には何かあったのでしょうか?
宮崎:
その渦中にいる方は気がつかないと思うんです。つまり、毎日テレビを見てるとか、日本の映画をいっぱい見ているとか、その人達は気づかないと思うんです。吹き替えのものを見てるとかね。
ぼくは東京と埼玉県の間を往復して暮らしていますけど、さっきも言いましたように、映画を見ていないんです。テレビも見ていません。自分の記憶の中によみがえってくるのは、特に「風立ちぬ」をやっている間じゅうよみがえってきたのは、モノクロ時代の日本の映画です。
昭和30年以前の作品ですよね。暗い電気の下で生きるのにたいへんな思いをしている若者や、いろんな男女が出てくるような映画ばっかり見ていたんで、そういう記憶がよみがえるんです。
それと、今の――失礼ですが、タレントさんとのしゃべりかたを比べると、そのギャップに愕然とします。何という存在感のなさだろうと思います。で、庵野も、スティーブン・アルバートさんも、存在感だけです(笑)。
かなり乱暴だったと思うんですけど、そのほうがぼくにとっては映画にぴったりすると思いました。
でも、ほかの人がダメだったとは思わないです。あの菜穂子をやってくださった人なんかは、みるみるうちに本当に菜穂子になってしまって、ちょっと愕然としました。そういう意味で非常に、『風立ちぬ』の映画はですね、ドルビーサウンドだけど、ドルビーではないものにしてしまう、周りから音は出さない。ガヤは二重にも三重にも集めてやるんじゃなくて。音響監督は2人で済んだと言っています。
つまり昔の映画はですね、そこでしゃべっているところにしかマイクが向けられませんから、まわりでどんなにいろんな人間が口を動かしてしゃべってても、それは映像には出てこなかったんです。その方が世界は正しいんですよね。僕はそう思うんです。それを24チャンネルになったら、あっちにも声を付けろ、こっちにも声を付けろ、それを全体にばらまく結果ですね、情報量は増えているけれども、表現のポイントはものすごくぼんやりしたものになっているんだと思います。
それで、思い切って、美術館の短編作品をいくつかやっているうちに、いろいろ試みていたら、これでいけるんじゃないかっていうふうに、私は思ったんですけど、プロデューサーがまったくためらわずに「それでいこう」と言ってくれたのが、ほんとうに嬉しかったですね。それから、音響監督もまさに同じ問題意識を共有できてて、それができた。こういうことって滅多に起こらないと、ぼくは思います。
それで、これも嬉しいことでしたが、いろんなそれぞれのポジションの責任者たちが、例えば色だとか背景だとか、それから動画のチェックをする人とか、それぞれいろんなセクションです。制作デスクの女性も、音楽の久石さんも……、って一番最後に言うのは問題があるんですけど。何かとってもいい、円満な気持ちで終えたんです。
こういうことは初めてでした。もっととんがって、ギスギスしたところを残しながら終わったもんなんですけども、こんなに、ぼくはつい、「ぼくのお通夜に集まったようなスタッフだ」と言ったんですけど、20年ぶり、30年ぶりのスタッフも何人も参加してくれてやりました。そういうことも含めて、映画を作る体験としては、非常にまれな、いい体験として終われたので、ほんとうに運がよかったというふうに思ってます。
――5年前よりやせているように思いますが、今の健康状態はいかがですか?
宮崎:
いまぼくは、正確に言うと63.2キロです。実は、ぼくは50年前にアニメーターになったとき57キロでした。それが60キロを超えたのは、結婚したせいなんですけど、つまり三度三度めしを食うようになってからです。一時期は70キロを越えました。そのころの自分の写真をみると「醜い豚のようだ」と思ってつらいんです。
映画を作っていくために、体調を整える必要がありますから、外食をやめました。それで、朝ご飯はしっかり食べて、昼ご飯は家内の作った弁当を持ってきて食べて、夜はうちへ帰ってから食べますけども、ご飯は食べないでおかずだけ食べるようにしました。別にきつくないことが分かったんです、それで。そしたら、こういう体重になったんです。これは女房の協力のおかげなのか、陰謀なのか分かりませんけど、これでいいんだと思ってるんです。
で、ぼくは最後57キロになって死ねるといいなと思っているんです。スタートの体重になって死ねりゃあいいと思ってます。あの、健康はいろいろと問題があります。問題がありますけれど、とても心配してくださる方々がいて、よってたかって何かやらされますので、しょうがないからそれに従ってやってこうと思ってますから、何とかなるんじゃないかと思います。いいですか、それで。
――今は健康ということですね。
宮崎:
んー、あのね、映画を1本作りますと、よれよれになります。それで、どんどん歩くと、だいたい体調が調ってくるんですけど、この夏はものすごく暑くて。上高地行っても暑かったんですよ。ぼくは呪われていると思ったんですけど。まだ歩き方が足りないんです。もう少し歩けば、もっと健康になると思いますが。
――「熱風」で憲法について発信した理由は? それから、星野社長に伺います。宮崎監督が「日本のディズニー」と称されることがありますが、そのように表現されることにどう感じますか?
宮崎:
熱風から取材を受けまして、ぼくは自分の思っていることを率直に喋りました。もう少し、ちゃんと考えてきちんと喋ればよかったんですけど、「あー、もう、ダメだよ」とかそういう話しかしなかったもんですから、ああいう記事になりました。別に訂正する気も何もありません。
じゃあ、それを発信し続けるかといわれても、ぼくはさっきも言いましたように、文化人ではありませんので、その範囲でとどめていようと思います。
あとの質問は、星野さんに。
星野:
実は「日本のディズニー」という言い方は、監督がしているわけではありません。2008年に公の場で、同じ質問が外国人特派員の記者からあったときに、監督がお答えになってるんでけども、ウォルト・ディズニーさんはプロデューサーであった。で、自分の場合はプロデューサーがいると。鈴木プロデューサーのことだと思うですけど。
で、ウォルト・ディズニーさんは、たいへん優秀なクリエイター、ナインオールドメン――9人のアニメーター。たいへん優秀な人材に恵まれていた。自分は、ディズニーではない、っていうふうに明確におっしゃっています。
わたし自身も、ディズニーには20年近くいましたし、ディズニーの歴史とか一生懸命勉強するなかで、全然違うなと感じております。そういう面では、日本のディズニーではないんじゃないかなと思っています。
――熱風の取材でしゃべろうと思ったのはなぜですか
それはですね、鈴木プロデューサーがですね、中日新聞で憲法について語ったんですよ。そしたら鈴木さんのところに、いろいろネットで脅迫が届くようになった。それを聞いて、鈴木さんに、冗談でしょうけど「電車に乗るとやばいですよ、ブスッとやられるかもしれない」というふうな話があってですね。
これで、鈴木さんの腹が刺されてるのに、こっちが知らん顔しているわけにはいかないから、ぼくも発言しよう、高畑監督にもついでに発言してもらってですね、3人いると的が定まらないだろうという話で、発言しました。それが本当のところです。ほんとに脅迫した人はどうも捕まったらしいですが、それは詳細は分かりません。
――作品のなか、監督のお言葉で「力を尽くして生きろ、持ち時間は10年だ」という言葉がありますが、監督の思い当たる10年とは、どの10年でしょうか。また、これから先の10年をどうなってほしいと願っていますか?
宮崎:
ぼくの尊敬している堀田善衛さんという作家が、最晩年ですけどエッセイで、旧約聖書の「伝道の書」というのを、「空の空なるかな」というエッセイと、もう1つありましたね……で、書いてくださったんです。そのなかに、旧約聖書の「伝道の書」の中にですね、「汝の手に堪ることは力をつくしてそれを為せ」ってあるんです。それだけじゃないんですけど、非常に優れた、わかりやすく、ぼくは堀田善衛さんが書いてくださると、「頭が悪いから、もう1回お前にも分かるように書いてやるから」って感じで書かれている気がしまして、その本はずっとわたしの手許にあります。
10年というのはですね、ぼくが考えたことではなくて、絵を描く仕事をやると38歳ぐらいにだいたい限界がまずきて、そこで死ぬやつが多いから気をつけろと、ぼくは言われたんです。自分の絵の先生にです。それで、だいたい10年ぐらいなんだなと思った。ぼくは18歳の時から絵の修業を始めましたから。そういうことをぼんやりと思って10年とつい言ったんですが。
実際に監督になる前に、アニメーションというのは、世界の秘密をのぞき見ることだ。風や人の動きやいろいろな表情や、まなざしや、体の筋肉の動きそのものの中に、世界の秘密があると思える仕事なんです。それが分かった途端に、自分が選んだ仕事が、非常に奥深くてやるに値する仕事だと思った時期があるんですよね。
そのうちに演出やらなきゃいけないとか、いろんなことが起こってだんだんややこしくなるんですけれども、その10年は何となく思い当たります。そのときは本当に自分は一生懸命やってたというふうに、まぁ、いまから言ってもしょうがないんですけども。
これからの10年に関してはですね、あっという間に終わるだろうと思っています。それは、あっという間に終わります。だって、美術館作ってから10年以上経ってるんですよ。ついこの間作ったと思っているのに。これからさらに早いだろうと思います。ですから、そういうもんだろうと(笑)。それが、わたしの考えです。
――長編映画の引退を奥さんにどう伝えたのですか? また、子どもたちに「この世は生きるに値する」ということを伝えることが根底にあるとおっしゃいましたが、この世をどう定義していますか?
宮崎:
家内には、「こういう引退の話をした」というふうに言いました。それで、「お弁当は今後もよろしくお願いします」と言って、「フンッ」って言われましたけど(笑)。
常日ごろから「この年になってまだ毎日弁当を作っている人はいない」って言われておりますので、「誠に申し訳ありませんがよろしくお願いします」と。そこまで丁寧に言ったかは覚えていませんが。というのはもう、外食は向かない人間に改造されてしまったんです。ずっと前にしょっちゅう行ってたラーメン屋に行ったら、あまりのしょっぱさにびっくりして。ほんとうに味が薄いものを食わされるようになったんですね。そんな話は、どうでもいいですけど。
「この世が生きるに値する」というご質問がありましたけど、ぼくは自分の好きなイギリスの児童文学作家で、もう亡くなりましたけど、ロバート・ウェストールという男がいまして、その人が書いたいくつかの作品の中に、ほんとうに自分の考えなければいけないことが充満しているというか、満ちているんです。
この世はひどいものである。その中で、こういうセリフがあるんですね。「君はこの世に生きていくには、気立てが良すぎる」。そういうふうに言うセリフがありまして、それは少しも褒め言葉じゃないんですよ。そんな形では生きていけないぞお前は、というふうに言っている言葉なんですけど。それは、ほんとうに胸打たれました。
つまり、ぼくが発信しているんじゃなくて、ぼくはいっぱい、いろんなものを受け取っているんだと思います。
多くの書物というほどじゃなくても、読み物とか、昔見た映画とか、そういうものから受け取っているので、ぼくが考案したものではない。
繰り返し繰り返し、この世は生きるに値するんだというふうに言い伝え、「本当かな」と思いつつ死んでいったんじゃないかというふうにね。それを、ぼくは受け継いでいるんだと思っています。
――鈴木さんにお尋ねします。引退発表をヴェネチアで行った理由を教えてください。
鈴木:
ヴェネチアでコンペの出品要請があったのは、かなり直前のことだったんですよ。社内で引退を発表し、今日公式発表するスケジュールは前から決めてきたんですけどね、そこに偶然ヴェネチアのことが入ってきたんですよ。で、ぼくと星野の方で相談しまして。ご承知のように、宮さんには外国に友人が多いじゃないですか。そしたら、ヴェネチアでそのことを発表すれば――言葉を選ばなきゃいけないんですけど、一度に発表できるな、とそういうふうに考えたわけなんですよ。
もともとこうも考えてたんです。まず引退のことを発表して、その上で記者会見すると。この方が混乱も少ないだろうと。当初は、東京でやるつもりでした。皆さんにFAXその他送って。ただ、ちょうどヴェネチアが重なったものですから、ジブリからも人が行かなきゃいけない。そこで発表すれば、いろんな手続きを減らすことができる。ただそれだけのことでした。
宮崎:
ヴェネチア映画祭に参加すると、正式に鈴木さんの口から聞いたのは今日が始めてです。なんか……、「え?」というふうに、もう星野さんが行ってるとか。ああそうなんだと、そういう感じでございまして。これは、もうプロデューサーの言うとおりにするしかありませんでした。
――富山県出身の堀田善衛先生がお話の中に出てきました。風立ちぬの映画の中でも「力を尽くせ」「生きねば」といったメッセージが込められていますが、堀田善衛から引き継いだメッセージや、どんな思いを込められて作られたのか教えてください。
宮崎:
自分のメッセージを込めようと思って映画って作れないんですよね。何か自分が「こっちでなきゃいけない」と思ってそっちに進んでいくのは何か意味があるんだろうけど、自分の意識では捕まえることができないんです。捕まえられるところに入っていくと、たいていろくでもない所に行くんで、自分でよく分からないことに入っていかざるを得ないんです。
それが、最後に風呂敷を閉じなきゃいけませんから、映画って。最後に未完で終わっていいんだったら、こんなに楽なことはないんですけど。しかも、いくら長くても2時間が限度ですから、刻々と残りの秒数は減っていくんですよね。それが実態でして。
セリフとして「生きねば」とかいうことがあったから、多分これは鈴木さんが『ナウシカ』の最後の言葉をどこかから引っ張り出してきて、ポスターにぼくが書いた『風立ちぬ』って字より大きく「生きねば」って書いて、「これは鈴木さんが番張ってるな」と僕は思ったんですけど(笑)。そんなことは、どうでもいいんですけど(笑)。
そういうことになって、ぼくが生きねばと叫んでいるように思われていますけど、ぼくは叫んでおりません(笑)。
でも、そういうことも含めて宣伝をどういうふうにやるか、どういうふうに全国に展開していくかというのは、鈴木さんの仕事として、死に物狂いでやってますから、ぼくはそれをもう、全部任せるしかありません。
そういうわけで、いつのまにかヴェネチアに人が行ってるという、その前に「なんとか映画祭にパクさんと2人で出ませんか」って言われて、「いや勘弁してください」とか。ヴェネチアについては何も聞かれなかったですけど、「そういえばそうですね」ってさっき言ってましたけど、しらを切ってますけど。
そういうことで・・・・・・。
鈴木:
コメント出してますよ、宮さん。
宮崎:
え?
鈴木:
ベネチアに関して。いま思い出しました。リド島が大好きと。
宮崎:
あ! ぼくはリド島が好きです(笑)。
そして、リド島とですね、カプローニの子孫、子孫っていったって孫ですけど、イタロ・カプローニって人ですけど、その人がたまたま『紅の豚』を見てですね、自分のじいさんがやってたカプローニ社の社史、会社の歴史ですね、飛行機の図面というか、わかりやすく構造図に書いたものが、こんな大きな本で、日本に1冊しかないと思いますけど、突然イタリアから送ってきまして、「いるならやるぞ」と書いてあったんです。そりゃ、日本語で書いてあったわけじゃないんですけど。ありがたくいただきますというふうに返事を書きましたけど。
それで、ぼくは「写真でみた変な飛行機」としか思ってなかったものの中の構造を見ることができたんです。ちょっと胸を打たれましたね。技術水準はドイツとかアメリカに比べるとはるかに原始的な、木を組み合わせるとかそういうものなんですけど、構築しようとしたものは、ローマ人が考えたようなことをやってるこの人は、と思ったんです。
それで、ジャンニ・カプローニっていう設計者は、ルネッサンスの人だと思うと非常によく理解できて。つまり、経済的基盤のないところで航空会社をやってくためには、相当はったりもホラも吹かないといけない。その結果作った飛行機が航空史の中に残ってたりするんだということが分かって、とても好きになったんです。そういうことも、今度の映画の引き金になっていますから。
溜まり溜まったものでできているものですから、自分の抱えているテーマで映画を作ろうというふうにね、あんまり毎度思ったことはありません。ほとんど、ぼくのところに突然送られてきた1冊の本とか、そういうものが、ずいぶん前ですよね、だから。そういうときに、蒔かれたものがいつの間にか材料になってくってことだったと思います。
――宮崎さんにとって堀田善衛とはどんな作家なのか教えてください。
宮崎:
さっき、経済が上り坂になって、どん詰まりになってとか、落っこてとかね、そういう話を、よく分かっているように言っていますけど、しょっちゅう分からなくなったんです。それで、『紅の豚』をやる前なんかも、本当に、世界情勢をどういうふうに読むか分からなくなっているときに、堀田さんってそういうときにさっと、短いエッセイだけど、何か書いたものが届くんですよ。
自分がどっかに向かって進んでいるつもりなんだけど、どこに行ってるんだかよく分かんなくなるようなことがあるときにね、見ると、本当にぶれずに、堀田善衛さんという人は、現代の歴史の中に立っていました。それは、見事なものでした。それで、自分の位置が分かることが何度もあったんです。
ほんとうに、堀田さんがひょいと書いた、「国家はやがてなくなるから」とかね、そういうことが、そのときの自分にとってどれほどの助けになったかと思うと、やっぱり大恩人の1人だというふうに、ぼくは今でも思っています。
――初期の作品は2とか3年間隔で発表されていましたが、今回は5年ということで、これは年齢によるもの以外に時間のかかる要因はあったのでしょうか?
宮崎:
いや、1年間隔で作ったこともあります。最初の『ナウシカ』……、『ナウシカ』はちょっと違うんですけど、『ナウシカ』も『ラピュタ』も『トトロ』も『魔女の宅急便』も、それまで演出をやる前に手に入れていたいろんな材料が溜まってまして、出口があったらばっと出て行くというふうな状態になってたんです。その後は、さぁ、何を作るか探さなきゃいけないという、そういう時代になったから、だんだん時間がかかるようになったんだと思いますけどね。
あとは、最初の「ルパン三世 カリオストロの城」というのは、4カ月半で作りました。それなりに一生懸命やって、寝る時間を抑えてでも何とかもつギリギリまでやると、4カ月半でできたんですが、そのときはスタッフ全体も若くて、それと同時に長編アニメーションをやる機会は生涯に1回あるかないかみたいな、そういうアニメーターたちの群れがいてですね、非常に献身的にやったからです。
それをずっと要求し続けるのは無理なんで。年もとるし、所帯もできるし、「わたしを選ぶのか、仕事を選ぶのか」みたいなことを言われる人間が、どんどん増えていくというね。今度の映画で、両方を選んだ堀越二郎を僕は描きましたけど、これは面当てではありません(笑)。
いや、まぁ、そういうわけで、どうしても時間がかかるようになったんです。と同時に、自分が1日12時間机に向かってても、14時間机に向かってても耐えられた状態ではもうなくなりましたから、実際、たぶん机に向かってた時間はもう7時間が限度だったと思いますね。あとは休んでいるとかおしゃべりしてるとか飯を食ってるとかね。
打ち合わせとか、これをああしろとか、こうしろとかいうことは、ぼくにとっては仕事じゃないんですよ。それは余計なことで、机に向かって描くことが仕事で、その時間を何時間とれるかという。
それがねぇ、この年齢になりますと、どうにもならなくなる瞬間が何度も来るというね。その結果、何をやったかといいますと、鉛筆をぱっと置いたらそのまま帰っちゃう。片付けて帰るとか、この仕事は今日でけりを付けようというのを一切あきらめたんです。やりっ放しです。やりっ放しで放り出したまま帰るということをやりましたけど、それでも、もう限界ギリギリでしたから、これ以上続けるのは無理だ。
じゃあ、それをほかの人にやらせればいいじゃないか、というふうなことは、ぼくの仕事のやり方を理解していない人のやり方ですから、それは聞いても仕方ないんです。そういうことができるなら、とっくのの昔にそうしてますから。
そういうわけで、5年かかったといいますけども、その間にどういう作品をやるかというのは、方針を決めて、スタッフを決め、それに向かってシナリオを書くということもやっています。やってますけど、でも『風立ちぬ』はやっぱり5年かかったんです。そういうことから考えますとですね、この『風立ちぬ』の後、どういうふうに生きるかっていうのは、これはまさに、いまの日本の問題で。
このまえ、ある青年がたずねてきて、「映画の最後で、丘をカプローニと二郎が下っていきますけど、その先に何が待っているかと思うと、ほんとうにおそろしい思いで見ました」っていう、これはびっくりするような感想だったんですけど、それはこの映画をこんにちの映画として受け止めてくれた証拠だろうと思って、それはそれで納得しましたが、そういうところに今、ぼくらはいるんだということだけは、よく分かったと思います。
なんか、質問に答えたことになるのかならないのか分かりませんけど、そいうことです。
星野:
最後に改めて、宮崎さんからあいさつをお願いします。
宮崎:
こんなにたくさんの方が見えると思いませんでした。本当に長い間、いろいろお世話になりました。もう二度とこういうことはないと思いますので、ありがとうごさいます。