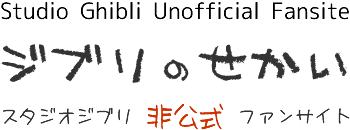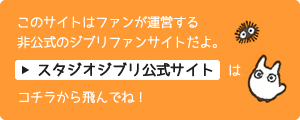スタジオジブリで、初めて長編制作に挑んだマイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット監督。8年の歳月を経て完成させたのが『レッドタートルある島の物語』です。
スタジオジブリで、初めて長編制作に挑んだマイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット監督。8年の歳月を経て完成させたのが『レッドタートルある島の物語』です。
2016年に行なわれた完成報告会見には、マイケル監督と共に、鈴木敏夫プロデューサーも登壇しました。
報告会見では、ジブリが初めて海外共同制作に挑んだことや、本作の設定や、本作を観た宮崎駿監督からの言葉なども披露されました。
ジブリからのオファーに有頂天になった
鈴木:
マイケル監督の『父と娘』という作品を観たのが、もう15年ほど前になります。それを観て僕は、この人に長編アニメ映画をつくってもらったら、一体どういうものが出来るんだろうと思いました。(『父と娘』は)非常に素朴だったんですよ。だから、今回、いろいろな記者の方に、「ヨーロッパの監督、スタッフで映画をつくる。とんでもないことをやられましたね」って質問をされたんです。最初は、それがぜんぜんピンとこなかったんです。けれど、改めて聞かれるとそういうことかなと思います。
マイケル:
本日は皆さん、ここに来てもらってありがとうございます。そして映画も観てもらって、ほんとうに感謝しています。今日は、個人的なことでも、映画についてでも質問があれば、喜んで答えたいと思っていますので、よろしくお願いします。
日本というのは、私にとって遠い国ではあるんですけれど、すごく心地がいい国なんです。なので今日、日本の皆さんに映画を観てもらえることを幸せに思っています。
――トロント国際映画祭出品、おめでとうございます。手応えはどうですか?
マイケル:
私はトロントには行ったことがないので、これから行くのが楽しみです。世界各国からマスコミの方、映画関係者がいっぱい来ると聞いています。ヨーロッパでつくられた作品が、北米という映画産業がしっかりした国で観てもらえることにとても感謝しています。
――すでにフランスとオランダなどでは公開されていると聞きました。観客の皆さんの反応はどうですか?
マイケル:
フランスでの公開は、まずカンヌで上映されたんです。そのとき、お客様からもほんとうに温かく、爆発的な反応があったと思っています。プレスからも温かく迎えられて、ポジティブな意見ばかりでした。ベルギーでもそうだったんですけれど、高評価を受けています。特に、オランダ人の映画監督ってあまりいないので、オランダ人にとってもオランダ人監督がこうやって映画をつくったということが、とても嬉しかったんだと思います。あとはドイツ語圏のスイスでも公開されたんですけれど、そこでの数字も健闘しているようです。
もちろん、アート作品ですので商業映画のような動員数があるわけではないんですが、アート作品として、なかなか健闘していると聞いています。
――まもなく日本公開です。
マイケル:
日本には、これまで観光や、ジブリさんとお仕事をするにあたって何度も来たことがあります。日本の匂いや日本人のしぐさなど、だいぶいろいろなことに慣れてきました。今回映画が完成して、日本の皆さんに映画を観て素晴らしい時間を感じてもらえたら、ほんとうに嬉しいと思っています。
――スタジオジブリから監督の打診があった経緯を教えてください。
マイケル:
実はジブリさんの方から何の予兆もなく、ある日突然、一通の手紙をもらいました。その中には、「一緒に映画をつくらないか、長編をつくらないか?」ということが書かれていました。それは、私の人生の中でも一番大きな衝撃だったと思っています。そのようなオファーを受けたときに「すぐにでも撮りたい!」と有頂天になったんですが、もしかすると「自分は勘違いしているだけかな、手紙の内容をわかってないんじゃないか」と自問自答したりもしました。でも、ほんとうにジブリさんから、そのようなオファーを受けたときは、地上1メートルぐらいのところを浮いて歩いているような、そんな感覚でした。
――鈴木プロデューサー、15年前にマイケル監督の作品を観たということですが、どんな気持ちで監督にオファーしたのですか?
鈴木:
「父と娘」を観て、一発で大好きになりました。観た回数は今日まで考えると100回は超えていると思います。というのは、時間がたったの8分間で、その中に人生の全てが織り込まれていて、人に観せたくなるんですよね。その作品を好きになるもう一つの大きな理由として、西洋の人がつくっているにもかかわらず、東洋の考え方が入り込んでいる作品だったんです。だから、ぼくらが非常に腑に落ちる作品だったです。そして、この人が、もし長編をつくったとしても、この精神は受け継がれるんじゃないかと思いました。西洋の人がつくったんだけれど、日本人、もっと言えば東洋人が観ても納得できるものができるんじゃないかと思ったんです。でも、つくるといっても彼はロンドンにいたし、どうやって製作するか悩んでいました。
実は、30年来、ジブリがお付き合いのあるフランスのワイルドバンチという会社がありまして、そこのプロデューサーで、ヴァンさんという、気心が知れている人がいました。彼が日本にやってきたときに、「提案がある」と言い、「父と娘」を観てもらったんです。そしたら、彼がいたく感心を示してくれたんです。それで、すかさず、「一緒にやらないか?」と言ったら、彼は、「一緒にやろう!」とすぐに言ってくれて、そこからスタートしました。
その後、さっきの手紙というのもいろいろあったんですけれど、なにしろ、日本とロンドン、フランスという距離で、どういうストーリーにしていくか、実際につくるときの創作の問題、どういうスタッフでつくるのか、それからお金の問題がありました。
今、ヨーロッパでは昔のようにフランス映画というのがあって、それをフランス人がお金を出して映画をつくる時代ではない。イタリア映画もそうなんですけれど。ヨーロッパ中の人がみんなで集まって一カ所でつくる時代なんですよ。これ、ヴァンさんが非常に苦労してくれたところなんですけれど、先ほどから名前がでているベルギーやいろんな国の人がフランスに集まってやっていくことになりました。でもそこにたどりつくまでにかなりの時間を要するんですよ。だから、実際の制作は2006年10月、企画の時点からだとそれこそ10年という歳月が経っていたんです。実際にこれでいこうと決めて制作に入ったのは、今から3年前なんです。
足かけ3年の期間をかけてこの映画をつくり、ほんとうの完成は、ぼくの記憶だと今年の3月だったと思います。
――マイケル監督、ストーリーの構想はどんなふうに練られたのでしょうか?
マイケル:
映画をつくるにあたって、「自分がこの映画のなかでどのようなエモーション、フィーリングを表現したいのか?」ということを考えました。そこで、一番最初に思ったのが、自然に対する尊敬の気持ちです。そういったものを映画の中で感じてもらえる作品にしたいと思いました。自然に対する尊敬の気持ちというは、ただ単に美しい夕日や美しい浜辺を絵に描いて観せるということではないんです。灰色の空や雨が降ってきた様子ですとか、また死んでいく生き物、そういう自然の輪廻を全体的に描くことによって観ている人たちが、無意識のうちに自然に対する尊敬の気持ちを感じてもらえたらなと思いました。そういったところが最初の出発点だったように思います。
あともう一つ、一人の男と一人の女が出会うシンプルなラブストーリーを描きたかったというのがあります。それは、仰々しいアイラブユーではなく、本当にシンプルな男と女のラブストーリーです。あとは、自分自身、子どもの頃から南の島に漂流する男の話というのが好きだったんです。私は、漂流する話でも島を男がどう受け入れて、男はどのように自然の一部になっていくかというのを描きたかったんです。
――マイケル監督の構想を受けて、どう思いましたか?
鈴木:
「岸辺のふたり」が一人の女性の一生を描くとしたら、今回の「レッドタートル ある島の物語」は一人の男の一生を描くんだなというのが、最初の感想でした。マイケル監督がその台本、シナリオ、ストーリーフォトなど、途中までできたものをどんどん送ってくれたんです。で、高畑監督を中心に、日本側のスタッフ7~8人でいろんな意見を出して話をしたんですけれど、「これはマイケルの一家の話だね」って、誰かが言いだしたんです。みんなそれに対して非常に納得しました。マイケルが自分の奥さんに対してどういう考えで、どういう態度で接しているか、全部わかる映画だねって(笑)。そういう話をしていました。
――スタジオジブリとは、どのように制作を進めてきましたか?
マイケル:
ジブリとのコラボレーションをするにあたって、まず私は、ジブリの意見を聞きたいと思っていました。これまで監督として短編はつくってきたんですけれど、短編というのはあまり他の人の意見は聞かないで自分一人でつくる傾向があったんですね。けれど、長編に挑戦するということで、いろいろな分野のいろいろな個性を束ねて、そういう人たちの意見を聞きながらつくらなくてはいけないというチャレンジでした。なので長編の経験が豊かなジブリのようなスタジオにアドバイスをもらうというのは、とても重要だと思ったんです。
このストーリーというのは自分の深いところからストーリーが湧き出ているんです。私の監督としての感性をさらけだし、苦しみをわかってくれるスタジオのプロデューサーは誰なのかということを考えたときに、やはりジブリは最高の私のサポーターだったと思っています。最初にジブリに「私たちは作家の選択をなによりも尊重します」ということを言われたんです。それは、当たり前のことに聞こえるかもしれませんが、必ずしも全ての国でそのように映画製作が行われているわけではないんです。もちろん、違うシステムを批判する気はないですが、高畑さんは私のそういう気持ちをわかってくれたのか、とても慎重に自分の意見を言ってくれました。「これは、あくまでも君の映画であるんだから」ということで、意見を言ってくれたんですね。私自身も攻撃的な相手との対立したコミュニケーションは好きではないんです。どちらかと言えば、意見を並べて一緒に静かに話し合っていろいろ決めていくほうです。そういうスタンスがもしかするとジブリさんのスタンスと合っていたのかもしれません。
――ジブリの中の雰囲気はどうだったのでしょうか? 観た方の反応はありますか?
鈴木:
ジブリのスタッフで『レッドタートル ある島の物語』を観ているのは、宮崎駿ですかね。実は今週月曜日にマイケルがジブリを訪ねてくれたんです。そのときに宮崎が応対して、三つぐらい話をしていました。一つは、「10年間、ほんとうにねばり強くがんばりましたね」とねぎらいの言葉でした。「10年間、いろいろあって、くじけそうになったこともあったでしょう。それを最後までやり通したっていうのは、まず第一に素晴らしい」ということを話していましたね。 二つ目は、これはぼくも聞いていて新鮮だったんですが、「とにかく今、世界のアニメーションの情勢に、日本のアニメーションはいい意味でも悪い意味でも、すごく影響を与えている。あなたの作品を観たときに、日本のそういう影響を一切受けていない、それは見事である。」ということを言っていました。
そして三つ目。今、日本の状況は、手描きのアニメーションからCGアニメーションへと移行の時期なんです。ジブリもどちらを選択するのか、非常に厳しい選択を迫られているんです。そういうときに宮崎駿は『レッドタートル』を観ながら、ぼくに「素晴らしいスタッフと作品をつくっている。このスタッフがほしい」と言いだしたんですよ(笑)。「このスタッフがいれば、僕もやれるかな」って、言いだしたんです(笑)。それが彼の感想でした。
――さきほど鈴木さんからこの映画は、マイケル一家が描かれているというお話がありましたが、それを聞かれて監督はどう思いましたか?
マイケル:
さきほど聞いてびっくりしました。確かに男と女が出会って幸せに生きるというのは、私の人生だったと思います。二人は恋に落ちる、私もそうだったんですね。きっと皆さんもそういう経験があると思います。あとこれは、アニメーターの悪いクセなんですが、私の作品の登場人物の男の子の絵を見ると、「あーマイケルの息子に似ているね」ってよく言われるんです。そして登場人物の男性もマイケルに似ているとよく言われます。これは、アニメーターの悪いクセで人物を描くときに、自分になぜか似せてしまうんですよね。
――今現在のスタジオジブリの制作体制と今後の作品づくりについてお聞かせください。
鈴木:
スタジオジブリも、気づいたら30年ちょっとの歴史があるです。その中で作品のつくり方は二つありました。これはジブリではないですけれど、『風の谷のナウシカ』から始まって、『魔女の宅急便』までは、作品ごとにスタッフを集めて、終わったら解散するというつくり方でした。ですが『おもひでぽろぽろ』からスタッフの社員化を始めたんです。いわゆる手描きからCGへの転換期の中で、対応策を考えなくてはいけなかったんです。
実は今、宮崎駿は長編からは引退しましたけれど、短編はやっているんです。美術館アニメーション、『毛虫のボロ』も12分間の作品で、これは実験的な要素も入っています。手でも描くし、CGも使っています。
今回の『レッドタートル ある島の物語』みたいに企画の段階に関わって、あとはヨーロッパでつくるということになると、これからは流動的になっていくと思うんですよね。
ジブリにもいろんなお話があります。CGをやっている方が「創作をジブリでやって、CGをうちの会社でやらないか? 一緒になってつくらないか」と言ってもらったりします。そういう中で、何を選択していくかは、これからまだまだぼくらは考えていかなくてはいけない時期だと思っています。
――お好きなスタジオジブリの作品を教えてほしいです。その作品にまつわる思い出などあれば教えてください。
マイケル:
一つの作品を選ぶのは、難しくてできないんですけれど、スタジオジブリの作品は、宮崎監督、高畑監督、他の監督の作品も全て好きです。ただ、一つ申しあげたいのが、私は宮崎監督が、子どもが新しい発見をするときの大きな喜び、大きな驚き、そういったものを汲み取って映画の中で表現するのが、ほんとうに素晴らしいと思います。小さいときに感じた喜び、驚きというのは、大人になるにつれて忘れてしまうんですけれど、そういったものをハッと思い返させてくれるところが素晴らしいなと思います。
高畑さんに関しては、『ホーホケキョ となりの山田くん』でいくつも俳句が出てくるというのが素晴らしいなと思いました。なぜなら、俳句は、簡潔で静粛で純粋な表現手段だと思うんですね。それを映画化するのはとても難しい。俳句という、映画にはなり得ないものを映画化したというところが大変素晴らしいと思います。特に大きな出来事がない、なんともないシーンに、ものすごく惹きつけられる、それが高畑さんの作品の素晴らしいところだと思います。
――もともとセリフがあるのに、「セリフをなしにした方がいいんじゃないか」、というのも高畑さんの意見だったそうですが、その他に高畑さんからのアドバイスはありましたか?
マイケル:
セリフをなくすというのは、最初はスタジオジブリの皆さんの意見だと思っていたんですが、先ほど鈴木さんとお話をしていて、鈴木さんがセリフをなくせということを言ったということをさっき聞きました。アニメーションをつくるときは、小さなディテールが大きな要素と同じぐらい大事になってくるんですね。高畑さんはアニメーターではないのですが、アニメーターの気持ちをよくわかっている方なので、高畑さんはディテールが大事な要素であるということを、とてもよくわかっている方です。
最初、私がとても好きな、月光の下、男と女が静かに草原の中を歩くというシーンがあったんです。それをなぜか違うシーンと差し替えたんですよね。すると高畑さんが「なんで差し替えちゃったの?」と言って、それで自分でも少し考えて「確かにあのシーン好きだったのに、なんで取ってしまったんだろう」と思って、また戻したということがあります。遠くから二人が空を飛ぶシーンがあって、それも1度抜いてしまったことがあったんですが、あとから「どうして遠くからのショットを取ったの? すごく素敵だったのに」と言ったので、差し替えたものをまた戻したという経緯があります。
――スタジオジブリとして初の海外共同制作ですが、今後も海外のクリエイターの方にオファーする可能性はありますか?
鈴木:
マイケルの場合は、すごく特別なものだと思っていたんですよね。海外の方と共同制作をやるっというのを計画的に考えたことは一度もないんです。だから、絶対にやらないというわけじゃなくて、どういう人と知り合うかわからない。それと、その人がどういうものをつくっているか、その内容が深く関係あると思うんです。あの人、すごく力があるから、すごく有名だからということだけでは、なかなか成立しないと思うんです。
今は『レッドタートル ある島の物語』を成功させて、その上で、ということなんですけれど、ご指摘があるように、いろんなところから話がきていないわけでもないんですよ。だから、そういうものをどうしていくかは、判断基準が難しいですよね。
――最後に、この映画を楽しみにしている観客の皆さんにメッセージをお願いします。
鈴木:
いろんな感想があると思います。ぼくがこの映画を観たときに真っ先に浮かんだのが、女性は偉いんだということです。そのおこぼれで、ついでに生きているのが男です。それを、あれだけそぎ落とした形で描かれると、感動せざるを得なかったということが言えます。
マイケル:
この映画をつくって感じたのが、スタジオジブリさんと仕事を始めたときは契約書もなく始めたんです。信頼関係があったから、お互いに何も決めずに仕事をすることができたんだと思うんです。もちろん、いろいろな意見の違いもありました。けれども、私は高畑さんを信頼していますし、鈴木さんを信頼しています。スタジオジブリの皆さんを信頼しています。
この作品は、ハンガリーのスタッフ、フランスのスタッフ、いろんなスタッフが関わってきました。すべての信頼関係を築いた上で仕事ができました。それを感じていただけたらなと思います。
 |
レッドタートル ある島の物語/マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット作品集 『レッドタートル ある島の物語』をはじめ、『アロマ・オブ・ティー』『父と娘(旧題:岸辺のふたり)』『お坊さんと魚』『掃除屋トム』『インタビュー』 を収録。 |