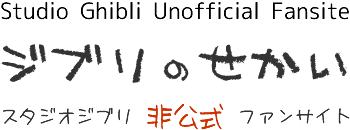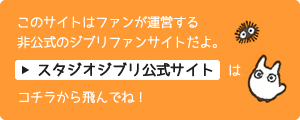『思い出のマーニー』の公開を記念して、映像配信サイト「GyaO!」で特別番組「ジブリのことが大すき。」が配信されています。その第一回目の放送の中で、西村義明プロデューサーが電話で参加しています。その電話インタビューの箇所だけ、文字に起こしました。
『思い出のマーニー』の公開を記念して、映像配信サイト「GyaO!」で特別番組「ジブリのことが大すき。」が配信されています。その第一回目の放送の中で、西村義明プロデューサーが電話で参加しています。その電話インタビューの箇所だけ、文字に起こしました。
MCにコトブキツカサさん、ゲストは伊藤綾子さん、若山あやのさん、山崎紗彩さん、さらに映像研究家の叶精二さんも参加しています。
「十一」は、11人兄弟の末っ子だから十一
若山:
十一さんは、なんで話さないんですか?
西村:
十一がなぜ話さないか。無口なんですよね。10年に一度しか喋らないっていう、そういう男なんですよね。
コトブキ:
10年に一度しか喋らないから、名前が「十一」なんですか?
西村:
元々は、原作『思い出のマーニー』の中に「ワンタメニー」ってキャラクターがいるんですよ。この「ワンタメニー」って「One too many」ってことなんですけど。11人兄弟の末っ子で、1人多すぎる、余分な子っていうことですね。11人兄弟の末っ子、だから11って書いて、十一って名前にしたんですけどね。
原作でも無口で、杏奈ちゃんと同じような、シンパシーを感じる存在です。
コトブキ:
杏奈が心を開かない人物だからこそ、十一と通じる部分があったんですか?
西村:
そうですね。映画の中でも、それを匂わせるようなシーンっていうのは、何個か用意されているんです。
北海道45か所のロケハンから選ばれた、理想の湿地帯
山崎:
北海道が舞台ですが、そういう場所はどうやって決めてるんですか?
西村:
今回は、原作の中にですね、「真珠色の空」という言葉が出てくるんですよ。
イギリスのどんよりとした、ちょっと雲がかかった涼しげな、そういうところを日本でも探したいと思って。日本で、どんよりとした感じで、涼しげなところで。映画のすごく重要な、湿地が出てくるようなところなんで。そういうの探していくと、北海道の道東に、そういう場所があることがわかったんですよね。
で、今回、北海道の道東を舞台に、『思い出のマーニー』を日本に置き換えてやることに決めました。
コトブキ:
いろいろな湿地帯の中から選ばれたということですか?
西村:
映画の絵コンテという作業が始まる前に、北海道45か所くらいロケーションハンティングをして、(北海道の)東の方に理想とするようなところがあったんで、それをいろいろと組み合わせて、架空の湿地の村を作りあげました。
コトブキ:
スタジオの女性陣から「楽しそう」という声が出たんですが、ロケハンは楽しいものですか?
西村:
ロケハンは、いろんな美味しいものを食べながらやるんで、楽しいですよ。
映画完成の4ヶ月間に決まった主題歌
伊藤:
主題歌がとても気に入って、いまも家で聴いたりしてるんですけど、この曲とはどんな出会いだったんですか?
西村:
あれは、プリシラ・アーンっていうアーティストが歌っているんですけど、ロサンゼルスの方で、スタジオジブリの作品が好きだったらしんですね。それを聞きつけたジブリ美術館のスタッフが、去年のクリスマスにジブリ美術館に招いて、クリスマスコンサートをやったんですよ。
そこに、ぼくはいなかったんですけど、今年の1月にジブリ美術館の館長が、プリシラ・アーンっていう凄くいいアーティストがいると奨めてくれて。
「Dream」という曲があるんですけど、それを聴いて、麻呂さんも凄く気に入って。それで、プリシラ・アーンさんに頼むことに決めたんですね。
伊藤:
ある程度製作が進んでいるところで、曲が決まったという流れなんですか?
西村:
そうですね。今回、ぼくが忙しすぎて、前作の『かぐや姫の物語』をやっていて、なかなか主題歌を決められなかったんですよ。それで、ギリギリのところで、映画を製作して完成する4ヶ月前くらいに決めましたね。もしかしたら、主題歌がなかったかもしれないというところで。ギリギリで、プリシラ・アーンが引き受けてくれました。
コトブキ:
前作よりは、今回の方が比較的スムーズにいったんですか?
西村:
そうですね。前作は、ちょっと大変な監督だったんで。8年間くらいかかってしまったんですけどね。
コトブキ:
映画祭の司会を何年かやらせてもらってまして、高畑監督にもインタビューしたのですが、「ほんとうに映画を終わらせたくなかった」と言っていたんですよ。楽しいから映画を完成させたくないと。そういった意味でも大変でしたか?
西村:
そうなんですよ。最後、映画が完成したじゃないですか。そのときに、「まだやってたい」と言ってたんで、こっちは「終わらせてやる」と思ってましたよ。
監督が実現したいことを共有し、協力するのがプロデューサーの仕事
叶:
お世話になってます、叶です。
西村:
何やってるんですか、そんなところで(笑)。
叶:
かなり世代の違う高畑さんとお組になって、それから世代の近い米林さんとお組になって、いろいろなものが違ったと思うのですけど、西村さんご自身はふたつの作品を経て、どういう変化がおありになったんでしょうか。
西村:
難しい質問ですね。結局、高畑さんとやったことも、麻呂さんとやったことも、あまり変わらなくて。監督が実現したい映画というものを、ちゃんと共有して、彼らが必要なことをやるっていうのが、ぼくの仕事ですから。それに関しては、全然変わらなかったですね。
高畑さんに関しては、凄く明快な「これしかやりたくないんだ」っていうのがあって、麻呂さんに関しては、仲間たちがいろんな意見を出し合ってくれて。和気あいあいとやってましたね、現場は。
コトブキ:
なぜ米林監督は、麻呂さんと呼ばれてるんですか?
西村:
入社して、最初の社員旅行のときに、先輩にいきなり「おまえ麻呂みたいだから、麻呂だ」って言われて。それから麻呂になっちゃいましたね。
若山:
「ふとっちょブタ」というセリフは誰が考えたんですか?
西村:
「ふとっちょブタ」は麻呂さんが考えました。原作では、そのままなんですよね。「Fat pig」って呼ばれてるんですよ、あの女の子は。それを日本語に直訳すると、ちょっと強すぎるんですよね。だから、若干かわいらしく「ふとっちょブタ」ってしました。
叶:
『アリエッティ』の試写のあとに、高畑監督の「この映画には、命をかけて良くしようとするプロデューサーがいない」という感想が印象に残って、今回の作品のプロデューサーをふたつ返事で受けたと伺っています。実際、命を掛けるっていうのは、西村さんの仕事に相応しい形容詞だと思うんですが、そのへんの命の掛けかたというのはどうだったんでしょうか。
西村:
命の掛けかたはですね、難しいんですけど、映画監督ってやっぱりみんな孤独なんですよ。
それは、高畑さんも宮崎さんも麻呂さんも、映画監督は最後は作品をすべて背負わなきゃいけないんですよ。そういうときに、傍らにいるプロデューサーは、その作品の責任の半分を背負ってあげるべき立場なんですよね。
麻呂さんの下した決断に、みんなが賛成できないときは、賛成できない人たちを説得に回ったり。麻呂さんが困ってるときに、アイディアを出してあげたりとか、監督と夫婦のような関係になって二人三脚で。
映画っていうのは、監督とプロデューサーにとっては子供みたいなもんなんで。命を掛けるっていうのは、そういう意味もありますよね。子供を育てるのに、親たちは一生懸命やりますから。そういう意味での命の掛けかたは、あると思います。
伊藤:
西村さんは、『思い出のマーニー』のなかで、どんなことを感じてもらいたいと思ってらっしゃいますか?
西村:
いろんなことを感じてもらいたいと思うんですけど、みんな杏奈ちゃんのような12歳の女の子だけじゃなくて、大人もいろんなことを不安に思うような時代だと思うんですよね。そういうときに、その不安の中で、人間が力強く生きていくには、傍らにいろんな人の愛情や支えがあることを、気づいてくれるような映画になってると思うので、そこらへんを感じてもらえたらなと思ってます。
コトブキ:
最後に、視聴者の方に一言お願いします。
西村:
ジブリの夏にふさわしい、長編アニメーション映画ができたと思っていて。女の子ふたりのお話が進むんですけど、実は中年のおじさんとかご家族が、凄く楽しんでくれているそうなので、ご家族そろって、もしくは友人と、恋人同士でも行ってもらえたらいいなと思います。是非、楽しんでください。
 |
宮崎駿全書 著者:叶 精二 本書は、長年にわたって宮崎駿監督をはじめ制作スタッフ・関係者に丹念に取材してきた資料を集大成したもので、「カリオストロ」から「ハウル」、「水グモもんもん」まで、宮崎駿監督の劇場用作品をあらすじ、制作の経緯、作品の源泉、制作スタッフ、声優、音楽と主題歌、宣伝と興行、主な批評、総評など14項目から多角的に解析する。 |