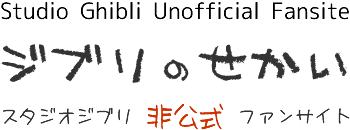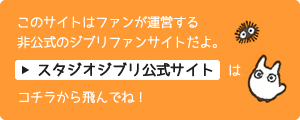世の中にたくさんの名作を残してきた高畑勲監督。スタジオジブリで宮﨑駿監督と一緒に、2枚看板として活躍してきたイメージも強くあるかと思いますが、その多くはジブリ設立以前の作品が締めています。
そこで、高畑さんが監督を務めた作品をご紹介します。
『太陽の王子 ホルスの大冒険』
公開:1968年7月21日
制作:東映動画
本作は高畑勲監督の長編アニメーションデビュー作。宮﨑駿監督は場面設計・美術設計・原画として、その能力を存分に発揮しました。
当初、制作費は7000万円の予算でしたが、1億3000万円を要しています。企画部長からは、「会社は君たちにプレハブを作ってくれといってるのに、君たちがやろうとしているのは鉄筋コンクリートだ」と指摘を受け、制作は一時中断。後に、宮﨑監督は「迷いの森」のシーンの削除が議論されたことを明かしています
『パンダコパンダ』
公開:1972年12月17日
制作:東京ムービー
当時、日本ではパンダブームが起こっており、それに合わせて公開された中編劇場アニメーション。原案、脚本、画面設定、原画を宮﨑駿さんが担当しており、『となりのトトロ』の原型とも評される作品です。
『パンダコパンダ 雨ふりサーカスの巻』
公開:1973年3月17日
制作:東京ムービー
本作品は東宝チャンピオンまつりの1本として公開されました。
大塚康生さんと、小田部羊一さんが作画監督を担当。美術監督は、小林七郎さんが担当。宮﨑駿さんが脚本・美術設定・画面構成を務めました。アニメーション史に残るレジェンドが参加されています。
『アルプスの少女ハイジ』
公開:1974年1月6日~12月29日
制作:ズイヨー映像
スイスの風景や日常生活の調査のためロケハンが行われ、高畑勲監督、宮崎駿さん、小田部羊一さん、中島順三プロデューサーらが参加しました。
20を超える言語に翻訳され、多くの国で放送されており、ヨーロッパにおいても「日本で制作されたとは思えない」と言われるほど、スイスの日常を正確に描きました。
錚々たる顔ぶれによって作られたことで、現在に至るまで語りつがれる名作となりました。
『母をたずねて三千里』
公開:1976年1月4日~12月26日
制作:日本アニメーション
本作は、作画監督・キャラクターデザインに小田部羊一さん、作画監督補佐に奥山玲子さん、場面設定・レイアウトに宮﨑駿監督、絵コンテには富野由悠季監督など、錚々たるメンバーが集まり制作されました。
絵コンテを担当した富野監督は、高畑監督の書いたシナリオが400字すべて一人のセリフだったことから、絵コンテを切るのに苦労したそうです。
『赤毛のアン』
公開:1979年1月7日~12月30日
制作:日本アニメーション
本作は、作画監督・キャラクターデザインに近藤喜文さん、場面設定・画面構成は1~15話まで宮﨑駿さん、美術監督は井岡雅宏さん、美術助手に山本二三さん、色指定に保田道世という豪華布陣で制作されました。
本作品は原作を忠実に、そのまま映像化した作品として高い評価を受けました。
高畑勲監督は、原作に忠実な作りにした理由として、会話劇の面白さやアンやマリラなどの登場人物が、それぞれの立場に立つことで二重に楽しめる構造など、原作の良さを活かすためとしています。
『劇場版 じゃりン子チエ』
公開:1981年4月11日
制作:東京ムービー新社
本作はアフレコで収録されましたが、芸人が声優を担当し、そのイキイキとした演技を目の当たりにした高畑勲監督は、先に音声を録って絵を合わせたほうが良い作品になると思ったことから、後の作品ではプレスコ収録を始めるようになりました。
大塚康生さんは「もっとも好きなアニメーション」と評し、ディズニーのナイン・オールドメンのメンバーでもあるフランク・トーマスとオリー・ジョンストンは、「私たちが、これまでに見た日本のアニメーションで最高の作品」と絶賛しています。
『セロ弾きのゴーシュ』
公開:1982年1月23日
制作:オープロダクション
オープロダクションによって、5年の歳月をかけて完成させた自主制作作品。原画を才田俊次さん、美術を椋尾篁さんがほぼ一人で担当するという、少数精鋭で制作された作品です。原作に登場する架空の楽曲「インドの虎狩り」「愉快な馬車屋」は、間宮芳生さんが作曲しています。
『柳川堀割物語』
公開:1987年
制作:二馬力
高畑勲作品としては唯一の実写作品です。当初は、アニメの舞台として柳川を登場させるつもりでしたが、水路再生の中心人物である広松伝さんに感銘を受け、柳川を主題にしたドキュメンタリーを作ることになりました。
本作は、宮﨑駿監督が『風の谷のナウシカ』で得た資金が投入され制作されました。しかも、高畑監督は用意された資金を使い果たしたため、宮﨑監督は自宅を抵当に入れる事態になっています。
『火垂るの墓』
公開:1988年4月16日
制作:スタジオジブリ
本作は『となりのトトロ』と2本立て上映で公開されました。観客動員数は約80万人、配給収入は5.9億円と振るわず、公開当時は興行的には当たっていません。しかし、後にジブリを代表する作品となりました。
当初は60分程度の中編を予定していましたが、88分に伸びており『となりのトトロ』と共に長編の2本立てになりました。
劇場公開時は彩色が間に合わず、一部色のない線画で公開されるという事態になりました。
『おもひでぽろぽろ』
公開:1991年7月20日
制作:スタジオジブリ
本作は、スタジオジブリが社員制度を導入してから作られた、初めての映画です。原作では、タエ子の子供時代だけの話でしたが、映画化に際して高畑勲監督のオリジナルで大人になったタエ子の物語が作られました。
大人のタエ子は27歳のOLで、1982年という設定。このパートは、演者の音声を事前にレコーディングしてからアニメを制作するというプレスコが用いられました。高畑監督にとって、本作が初めてのプレスコです。
『平成狸合戦ぽんぽこ』
公開:1994年7月16日
制作:スタジオジブリ
本作は配給収入で26.3億円(興収換算44.7億円程)を記録し、その年の邦画最高のヒット作品となっています。
また、実写映像やCGの使用や、ナレーションなど、ジブリ作品としては初めて採用された作品です。
表現方法を実験し続けてきた高畑勲監督らしい、初めての試みに溢れた作品でした。
『ホーホケキョ となりの山田くん』
公開:1999年7月17日
制作:スタジオジブリ
本作は、興行的に当たりませんでしたが海外での評価は高く、『スターウォーズ』や『トイ・ストーリー3』の脚本家マイケル・アーントに大きな影響を与えています。
スタジオジブリとしては初めて、この作品でセル画を一切使用しないデジタルで制作されました。デジタルによって水彩画のような彩色を実現するために、1コマにつき、実線、塗り、マスク処理用の線と、合計3枚が必要になり、作画枚数17万枚となっています。
『かぐや姫の物語』
公開:2013年11月23日
制作:スタジオジブリ
本作においても、『ホーホケキョ となりの山田くん』で導入された、水彩画風の手描きの一枚絵が動く作風で制作されました。
そのため、実線動画、塗線動画、模様作画と3種類の作画によって制作されました。総作画枚数は237,858枚と、ジブリ作品の中で飛びぬけて多い枚数となっています。