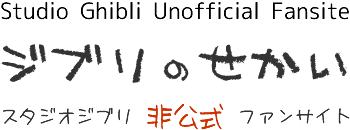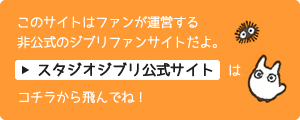新海誠監督が、8月30日にX(旧Twitter)にてスペースを行い、『君たちはどう生きるか』の感想を話しました。
映画の内容には触れていませんが、今回の宣伝しないという公開方針について、新海監督ならではの視点から語られています。
『君たちはどう生きるか』のお話の部分だけ文字に起こしました。
東宝の映像事業部・宣伝プロデューサーの弭間さんと、新海監督の対談となります。
自分が作っているものを、否が応でもふり返らなきゃいけない
新海:
他のアニメーション映画の話をする機会っていうのは、あまりないし。全部自分に跳ね返ってきてしまうので、「じゃあ、おまえの映画はどうなんだ」っていうことになるので、基本的にはあまりお話してないんですけど。
『君たちはどう生きるか』は、ぼくは初日に観てまいりました。弭間さんも初日に観たって言ってましたよね?
弭間:
我々も配給会社として、(事前に)観て仕事しないといけないんじゃないかと思うんですけど、今回はほんとうに限られた数名しか弊社の中でも観れた人はいなくてですね。
新海:
東宝の社長と会長にお誘いいただいて、一緒にご飯をいただく機会があるじゃないですか。そのときに、社長と会長に、『君たちはどう生きるか』は観たんですか?ってきいたら、「わしらも観とらん」って言ってましたよね。
弭間:
そうなんですよ。
新海:
マジかと(笑)。
弭間:
ほんとうにうちの会長も社長も、朝8時、9時の上映に予約をして。「いちばん早い回は何時ですか?」って秘書から連絡がきて(笑)。
「ちょっとスケジュール抑えなきゃいけなくて」みたいになっていたんです。
新海:
どこで観たんですか? 日比谷?
弭間:
そうですね、日比谷のTOHOシネマズ。朝一の回で。
新海:
やはり、そこは松竹とか、そういう映画館じゃないんですね(笑)。
弭間:
そりゃそうですわ(笑)。
会社の目の前なんで、そこで観てましたね。
新海:
ぼくも拝見して、圧倒されました。凄かったですね。凄まじいと思いました。
ずっと何かを突き付けられるような、「おまえはそれで良いのか?」と。ずっとお説教されているみたいな気持ちで。自分が作っているものを、否が応でもふり返らなきゃいけないような作品だったなと思って。とにかく圧倒されたし、揺さぶられたし、観終わったあとに自分が次にどんな作品を作れば良いのか、よりわからなくなるような、そんな作品でした。何かわかりやすい羅針盤のような映画ではなかったですよね。
弭間さん的にはどうでしたか?
弭間:
どんな話なのか、誰が声をやってるのかも知らない状態だし。もちろん、主人公はこの子なんだな、っていうのはわかるんですけど、どこに連れていかれる話なんだろうっていうのも、ずっとわからず「どういう話?」っていうハテナが、頭の中にずっとあったなっていう。
宣伝しないのは背筋が震えるような怖いこと
新海:
いろんなことを考えさせられますよね。どこに連れていかれるかわからないって、弭間さんがおっしゃってましたけど、けっこう映画を作るうえでも、いつも気にしていることなんですよ。観客って、常になにかを予想しながら観てるんだと思うんですよ。こう来たんだからこうなるだろうとか、こういう展開に違いないとか。で、思い通りにきたとか喜んだり、思いとまったく違うものがきて、どんでん返しがあって、そこに興奮したりするわけですよ。だから、ミスリードすることも含めて、何かを予想させる、どこに連れて行こうとしているのかというのを感じさせることは、普通に映画を作るときは大事なことなんですよ。
ぼくも脚本を書くときは、難しいなと思いながら意識してるんですけど。
でも、『君たちはどう生きるか』は、そういうセオリーからも、まったく外れていた映画だったので。とにかく衝撃でしたね。それでも、ぼくは最後まで画面に引き付けられてしまったので、こういう引き付け方があるんだなと思いました。
圧倒されたのと同時に、とても寂しい映画だなと思ったんですよね。なんで寂しいんだろうと思ったときに、映画の内容にも関係するんですけど、それよりもむしろ公開のされかたとか、告知の仕方。今回の『君たちはどう生きるか』って一切宣伝していないじゃないですか。そのことについて、思うことがたくさんありました。弭間さんも、ずっと宣伝プロデューサーで、『すずめの戸締まり』もやっていただいて、ぼくたちずっと一緒に映画を宣伝してきたじゃないですか。
で、映画って作るのが半分で、届けるのが半分じゃないですか。やっぱり力点としては。当たり前ですけど作ってる側も、届けるために作るわけじゃないですか。それと同時に、映画ってちょっと広いビジネスだったりもするから、宣伝も含めて一つのシステムというか、循環している大きな世界で、映画を作ったあと、いろんな宣伝プロデューサーとか、いろんなメディアの媒体の人とか、記者さんとか、地方のアナウンサーの方とか、映画ライターの方とか、いろんな映画興行主さんとかとの関係を、一作一作ごとに積み重ねていくわけですよね。ぼくたちは、ずっとそれをやってきて、海外でもそれを積み重ねてきて。それをやるのって観客に届けたいからでもあるし、「次の作品もお願いします。一緒にやりましょう」っていう関係性を積み重ねていくために…、スタッフとの関係性を積み重ねていくための宣伝もあると思うんですよね。お客さんに届けるのと同じくらいの力点というのか、意味があってやってるんですけど、今回のジブリの作品は、それを一切やらないわけじゃないですか。
そのことが、何かの終わりのようなことをどうしても連想しますよね。内実のところは、ぼくは存じ上げませんけれど、「もう、次は良いんだ」ってもしかしたら思ってらっしゃるのかもしれないし、これがいよいよ最後なんだっていうふうに思って、だから宣伝を積み重ねなくても良いし、…そうなんだとしたら、やはり寂しいなと思うんですよね。
自分がモノを作るときの人生まで重ねて観てしまうというか、いつか自分たちも宣伝ってとても大事だと思ってやってきたけど、「でも、もういいや」と「やらなくていいや」と、「作品さえ作れれば、それでいいや」という気持ちになっていったとしたら、凄まじいことだし、けっこう背筋が震えるような怖いことだなと思うんです。孤独な行為だなと思うんですよね。その強烈な孤独さみたいなものの、今回の公開のされかたからも突き付けられるような気がして、「あぁ、寂しいな」というふうに思った。
あとね、弭間さんとお話したいんですけど、宮﨑駿監督の前作『風立ちぬ』って、2013年の公開ですよね。ぼくたちの映画の『言の葉の庭』と同じ年だったんですよ。
で、『言の葉の庭』のとき、ぼくたちはすごく小さなスケールで映画の興行をやっていて、全部の映画館。23館の映画館を全部自分たちの足で回るんだっていうことを…あのときは広告宣伝費っていうのは、ぼくたちにはそんなになかったから、わりと足で回って一所懸命、観てほしくて宣伝してたんですよね。で、『言の葉の庭』の舞台挨拶に行ったときに、同時に『風立ちぬ』もやっていて。
弭間:
『風立ちぬ』のほうが、公開がちょっと後だったんです。7月20日公開で、『言の葉の庭』のちょっと後だったんです。
新海:
そうですそうです、『言の葉の庭』をやっているときに、『風立ちぬ』の予告編が流れていたんですよね。その予告編が、『言の葉の庭』の上映後に掛けていたんです。
いま思うと、ちょっとビックリするような手法なんですけど。それは、『言の葉の庭』だけではなくて、たぶんTOHOシネマズを中心に、当時やっていた多くの映画で、上映前じゃなくて上映後に、スタッフロールが終わった後に、『風立ちぬ』の予告編を流していたんですよね。しかも、4分間。けっこう長い予告編だったんです。で、ぼくはそのときにショックを受けて、弭間さんに「これはどういうことなんでしょうか?」とお話をさせてもらったりしたんですけど、
弭間:
めちゃくちゃ怒られました。
新海:
ぼくに限らず、他の映画の監督もみんな、ちょっと怒ったと思いますよ。
だって、映画を観てもらって、エンドクレジットを観て、『言の葉の庭』は楽しかったなって思ったあとで、『風立ちぬ』で上書きしていくんですよ。しかも、4分ですから。あの予告編はとても良くできていたので、みんな映画館を出るときに『風立ちぬ』が楽しみだっていう気持ちで、あるいは『風立ちぬ』をやるんだ、っていう気持ちで映画館を出て行ったのが、『言の葉の庭』の上映をやっているときだったんですよね。
ですから、ぼくは舞台挨拶に立つときに、『風立ちぬ』の予告編を観たあと、舞台挨拶に立って。で、劇場の皆さんに、『風立ちぬ』楽しみですね、って話をしてから『言の葉の庭』の話をしたんですよね(笑)。
弭間:
私たちも、袖で待っているときに、エンドロールが終わったときに「あれ?」って思って。
新海:
そう、知らなかったんですよね。
弭間:
驚きました。
寂しい映画だなと思った
新海:
弭間さんには、舞台挨拶の前だけでも良いから、『風立ちぬ』の予告を外してくれっていうふうにお願いして…。で、その後、全部の映画館から外れましたよね。
でも、あのとき思ったのは、ぼくは『風立ちぬ』は素晴らしい映画だと思ったし、必死にどんな手を使ってでも、観てほしいと思っている映画なんだなと。あるいは、日本国民は観るべきだ、国民映画なんだっていうふうに、ジブリ自身が作り手が思っているから、ああいうことができるんだって思ったんですよ。
だから、それってジブリ以外には許されない、できないことだろうし、思いついたとしてもやらしてもらえないことでしょうから。これは凄い映画だから人に観てほしいとか、あるいは沢山の人に観てもらうことで、世の中を変えることができる、そのくらいの気持ちがあって。『風立ちぬ』や、その前の作品からジブリはずっとそうでしたけど、ほんとうに大々的なキャンペーンをやって告知をしてきたじゃないですか。あれは、いったい何だったんだと。あのときの強い気持ちというか、強烈な「あなたに観てほしいんだ」という、「こっちを見てください」とこちらの顔を覗き込むような、ああいう気迫みたいなものから…10年が経って、今回はまったく無いわけじゃないですか。
極端な言い方をしてしまえば、こっちを見てくれてない感じがしたんですよ。「観てくれ」って言われてないから。こっちのことも必死に目を引くような映画って愛おしいし、「じゃあ、観るか」という気持ちになる。やりすぎると「観ない」ってなるから、宣伝の難しいところだと思うんですけど。でも、『風立ちぬ』までの必死になって、いろんな人の目を引き付けようとしていた、あのジブリが圧倒的だったので、そういうものが無くなったことも寂しいなと。
ですから、見せ方も含めて、内容も圧倒的なものはあるけれども、やっぱり寂しい映画だなと思いました。
弭間:
わたしは作品の担当ではないので、ジブリの鈴木敏夫さんが思ってらっしゃることを直接きいているわけではないんですけど。狙いという部分では、ほんとうにまったく何の前情報もない状態で観てほしいって。誰が声をやっているからとか、こういう主人公のこういうお話なんですとか、そういった情報がまったくない状態で観たときの、初めての新鮮な気持ちを大事にしてほしいんだ、というお気持ちで宣伝をしない、予告編を作らないし、掛けない。予告を出してしまうと、どういうルックなのかというのは、どうしても見えてしまうでしょうし。そこにかかる音楽は、そういう雰囲気で、それが劇伴とか、本編で使われる曲じゃなかったとしても、そういう曲が似合うものなんだという、何かしら先入観ができてしまう。そういうことでも、宣伝をしないという方針というふうに、わたしたちは聞いていたんですけど。
新海:
普通にはできない体験をぼくたちは経験できましたよね。一切何も知らない状態で……。
弭間:
主人公は誰?って思うじゃないですか(笑)。あのポスターの鳥が出てくるかどうかは、わかりませんって言いながら、劇場の興行の皆さんと話してました。
「弭間さん、ほんとうに知らないんですか? なにも観てないんですか?」って言われて、映画を興行されてる皆さんのところに行って、「延期とかじゃなくて、ちゃんとやるんです」って言って。「でも、何も来ないですよね。ポスター1枚来ただけで、チラシも予告も来ないじゃないですか」みたいな。「大丈夫です、ちゃんとやるんです。こういう方針です」と言って回ったりして、大々的に(劇場を)あてていただくってことをやったんですけど。監督がおっしゃるように、ほんとうに何もしないで、この日に久しぶりに宮﨑駿監督の最新作をやるんだよっていう。わたしは、宮﨑駿監督は大勢に観てほしいと思って作っていると思うし、わたしたちもそのつもりで届ける気はあるんですけど、それがお客さんたちのところに届いていないんじゃないかっていう不安がちょっとあったりとかして、せめて公開日をお伝えする、延期とかじゃないです、何も情報はないけどそれは意図的なんです、っていうのをもっと表に出したいっていうのがあって、それをご提案したんですけど、「いや、良いんだ。やらないんだ」という方針でいらっしゃったので。
新海:
もちろん、いろんな考え方がありますし。今回は普通ではやらないことをやられていて、大きな巨大な成果を出してらっしゃるのも確かなので。自分たちに同じことはできないので、ですから刺激にもなったし、興味深かったんですけれども、先ほど話したような感覚はありましたね。でも、楽しませていただきました。
共通のスタッフもお世話になったりしているし、ずっとぼくもワクワクして待っていた映画だったので、観ることができて感無量ではありました。