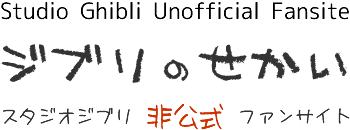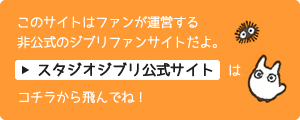スタジオジブリの最新作が、発表されました。
次回作は、宮崎吾朗監督の『コクリコ坂から』だそうです。
「コクリコ坂から」は、「なかよし」(講談社刊)で1980年1~8月号に連載されていた高橋千鶴・佐山哲郎(原作)の少女漫画が原作。平凡な女子高生の小松崎海が、新聞部の風間俊や生徒会長の水沼史郎のペースに巻き込まれながら、ドタバタな日常生活をおくる姿を描く。笑いあり、涙ありの内容で、駿監督が長年にわたって推薦していたことでも知られている。
「コクリコ坂から」は、2011年夏に全国で公開。
宮崎駿監督が、『コクリコ坂から』について、企画のための覚書を発表しています。
「港の見える丘」 企画 宮崎駿
1980年頃『なかよし』に連載され不発に終った作品である(その意味で「耳をすませば」に似ている)。高校生の純愛・出生の秘密ものであるが、明らかに70年の経験を引きずる原作者(男性である)の存在を感じさせ、学園紛争と大衆蔑視が敷き込まれている。少女マンガの制約を知りつつ挑戦したともいえるだろう。
結果的に失敗作に終った最大の理由は、少女マンガが構造的に社会や風景、時間と空間を築かずに、心象風景の描写に終始するからである。
少女マンガは映画になり得るか。その課題が後に「耳をすませば」の企画となった。「コクリコ坂から」も映画化可能の目途が立ったが、時代的制約で断念した。学園闘争が風化しつつも記憶に遺っていた時代には、いかにも時代おくれの感が強かったからだ。
今はちがう。学園闘争はノスタルジーの中に溶け込んでいる。ちょっと昔の物語として作ることができる。
「コクリコ坂から」は、人を恋(こ)うる心を初々しく描くものである。少女も少年達も純潔にまっすぐでなければならぬ。異性への憧れと尊敬を失ってはならない。出生の秘密にもたじろがず自分達の力で切りぬけねばならない。それをてらわずに描きたい。
「となりのトトロ」は、1988年に1953年を想定して作られた。TVのない時代である。今日からは57年前の世界となる。
「コクリコ坂から」は、1963年頃、オリンピックの前の年としたい。47年前の横浜が舞台となる。団塊の世代が現代っ子と呼ばれ始めた時代、その世代よりちょっと上の高校生達が主人公である。首都高はまだないが、交通地獄が叫ばれ道も電車もひしめき、公害で海や川は汚れた。1963年は東京都内からカワセミが姿を消し、学級の中で共通するアダ名が消えた時期でもある。貧乏だが希望だけがあった。
新しい時代の幕明けであり、何かが失われようとしている時代でもある。とはいえ、映画は時代を描くのではない。
女系家族の長女である主人公の海(うみ)は高校二年、父を海で亡くし仕事を持つ母親をたすけて、下宿人もふくめ6人の大世帯の面倒を見ている。対する少年達は新聞部の部長と生徒会の会長。ふたりは世間と大人に対して油断ならない身がまえをしている。ちょっと不良っぽくふるまい、海に素直なアプローチなんぞしない。硬派なのである。
原作は、かけマージャンの後始末とか、生徒手帖が担保とか、雑誌の枠ギリギリに話を現代っぽくしようとしているが、そんな無理は映画ですることはない。筋は変更可能である。学園紛争についても、火つけ役になってしまった自分達の責任を各々がはっきりケジメをつける。熱狂して暴走することはしない。何故なら彼等には、各々他人には言わない目標があり、その事において真摯だからである。
少年達が遠くを見つめているように、海もまた帰らぬ父を待って遠い水平線を見つめている。
横浜港を見下ろす丘の上の、古い屋敷の庭に毎日信号旗をあげつづけている海。
「U・W」旗――(安全な航行を祈る)である。
丘の下をよく通るタグボートのマストに返礼の旗があがる。忙しい一日が始まる朝の日課のようになっている。
ある朝、タグボートからちがう信号が上る。
「UWMER」そして返礼のペナント一旒(いちりゅう)。誰か自分の名前を知っている人が、あのタグボートに乗っている。MERはメール、フランス語で海のことである。海はおどろくが、たちまち朝の家事の大さわぎにまき込まれていく。
父の操るタグボートに便乗していた少年は、海が毎日、信号旗をあげていることを知っていた。
(ちょっとダブりますが)
舞台は、いまは姿を消した三島型の貨物船や、漁船、はしけ、ひき船が往来する海を見下ろす丘の上、まだ開発の手はのびていない。祖父の代まで病院だった建物に、和間の居住部分がくっついている。学校も一考を要する。無機的なコンクリート校舎が既にいくらでもあった時代だが、絵を描くにはつまらない。登校路は、まだ舗装されていない道も残り、オート三輪やらひっかしいだトラックが砂埃(すなぼこり)をあげている。が、ひとたび町へおりると、工事だらけの道路はひしめく車で渋滞し、木製の電柱やら無秩序な看板がひしめき、工場地帯のエントツからは盛大に黒煙、白煙、赤やらみどり(本当だった)の煙が吐き出されている。大公害時代の幕がきっておとされ、一方で細民窟が存在する猛烈な経済成長期にある。横浜の一隅を舞台にすることで下界の有様がふたりの直面する世間となる。その世界を俊と海が道行をする。そこが最後のクライマックスだ。
出生の秘密については、いかにもマンネリな安直なモチーフなので慎重なとりあつかいが必要である。いかにして秘密を知ったか、その時ふたりはどう反応するか。
ふたりはまっすぐに進む。心中もしない、恋もあきらめない。真実を知ろうと、ふたりは自分の脚でたしかめに行く。簡単ではない。そして戦争と戦後の混乱期の中で、ふたりの親達がどう出会い、愛し生きたかを知っていくのだ。昔の船乗り仲間や、特攻隊の戦友達も力になってくれるだろう。彼等は最大の敬意をふたりに払うだろう。
終章でふたりは父達の旧友の(俊の養父でもある)タグボートで帰途につく。海はその時はじめて、海の上から自分の住む古い洋館と、ひるがえる旗を見る。待ちつづけていた父と共に今こそ帰るのだ。そのかたわらにりりしい少年が立っている。
原作のエピソードを見ると、連載の初回と二回目位が一番生彩がある。その後の展開は、原作者にもマンガ家にも手にあまったようだ。
マンガ的に展開する必要はない。あちこちに散りばめられたコミック風のオチも切りすてる。時間の流れ、空間の描写にリアリティーを(クソていねいという意味ではない)。脇役の人々を、ギャグの為の配置にしてはいけない。少年達にいかにもいそうな存在感がほしい。二枚目じゃなくていい。原作の生徒会会長なんか“ど”がつくマンネリだ。少女の学校友達にも存在感を。ひきたて役にしてはいけない。海の祖母も母も、下宿人達も、それぞれクセはあるが共感できる人々にしたい。
観客が、自分にもそんな青春があったような気がして来たり、自分もそう生きたいとひかれるような映画になるといいと思う。