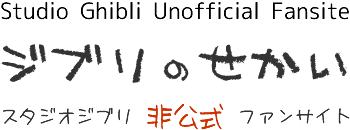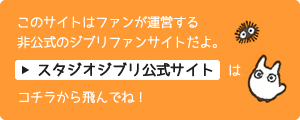宮崎駿・高畑勲両監督の作品を作ることでスタートしたスタジオジブリですが、近藤喜文監督の『耳をすませば』は、なぜ作ることになったのでしょうか。
宮崎駿・高畑勲両監督の作品を作ることでスタートしたスタジオジブリですが、近藤喜文監督の『耳をすませば』は、なぜ作ることになったのでしょうか。
そこには、近藤喜文監督の才能をいちばん高く評価していた、宮崎駿監督の想いがありました。
「近藤喜文ここにあり」という仕事をさせたかった
宮崎監督が感じた、近藤さんの才能には、絵の気持ちよさと、スカッと抜けた健やかさがあると言います。そういう近藤さんの才能を活かした、「近藤喜文ここにあり」という仕事をさせたかったと、宮崎監督は後に語っています。
近藤さんは、『赤毛のアン』『火垂るの墓』『おもひでぽろぽろ』と高畑勲作品に数多く参加してきました。しかし、宮崎監督は、この作品では近藤さんの持ち味を活かしきれていないと感じたそうです。
一緒に仕事がしたい。近藤さんに、何か作らせたい。ずっとそういう気持ちを持っていた宮崎監督に、ようやく巡ってきた機会が、『耳をすませば』でした。この企画は、宮崎監督が考えたものですが、どのように持ち出されたのでしょうか。
近藤さんは、ほんとうは児童書が好きなのだけれど、それだと華がないかもしれない。作品にツヤが出ないかもしれない。そう思った宮崎監督は、別の企画を探すことになります。
山小屋で出会った、柊あおいの『耳をすませば』
原作の『耳をすませば』とは、宮崎駿監督の義理のお父さんの信州にあるアトリエで、出会うことになります。
宮崎監督は、夏になると毎年このアトリエで過ごしていたらしく、そのときは仲間を呼んで大勢で過ごしていたといいます。
そこには、若かりし押井守監督や、庵野秀明監督、鈴木敏夫さん、そしてまだ子供だった宮崎吾朗監督もいたそうです。
そのアトリエは和風の日本家屋で、電話もなく、新聞も取っていないので、世間から隔離されたような場所でした。昼間は、周辺の散策をして、夜になると何もすることがなくなります。すると、退屈になった宮崎監督が、何かないかと部屋の奥を探していたら、見つけ出したのが漫画雑誌「りぼん」でした。
そのアトリエは、宮崎監督の親戚が、入れ替わり立ち代わり集まる場所だったため、姪っ子の置いていったものが残っていました。
そこで宮崎監督が読み始めたのが、まだ連載開始されて間もない、2、3話目の『耳をすませば』です。それを、その場にいたみんなで回し読みをしていきます。そして、宮崎監督は、「これの前はどうなってたんだろう?」と言い出しました。その展開を、ひとしきり喋るという遊びをしていたそうです。個性の強い演出家が集まっていたので、さぞ盛り上がったことでしょう。
そして、夏が終わり、東京に戻ったとき、宮崎監督は、『耳をすませば』の単行本をスタッフから借りて読みました。当然ながら、自分の考えていた展開と違っているわけですが、宮崎監督の中にこの作品が、とても印象深く残ることになります。
それから、10年余りの月日が流れ、近藤喜文監督には『耳をすませば』が向いているのではないかと思い出します。
小品として作り始めた『耳をすませば』
近藤さんは、アニメーターとしては優秀だけれど、監督としてやっていくときに、どのようなやり方が良いだろうか。宮崎監督は考えました。
映画を作るうえで、二通りのやり方があります。プロデュースサイドで企画を立て、シナリオ等を作ってから、監督に手渡すという、企画中心主義。もしくは、監督にすべてをゆだねて作るという、監督中心主義。宮崎・高畑両監督は、後者で作られています。
しかし、近藤さんは、今回が初監督の作品となるため、企画中心主義で作られることになりました。シナリオ・絵コンテは、プロデュースサイドで作り、それを監督に提供するという流れとなります。そこで、宮崎監督は、本作においてはプロデューサーの一人として、絵コンテを描くことになりました。
宮崎監督はこれまで、スタジオジブリでは大作ばかり作ってきたと感じており、「小品を作ろう」と言い出します。近藤さんには、それが向いていると感じていたようです。
そのためには、何をする必要があるのか。
ジブリ作品の絵コンテは、カメラワークの役割も果たしているため、他のアニメーション会社よりも、少し大きな絵コンテ用紙が使われているそうです。それを、宮崎監督は、テレビ用の小さなものに変更します。
物理的に小さくすることで、描き込み量が減るため、作画も楽になるだろうと考えたのです。作品内容が小品ならば、作画期間も短くしなければいけない。そのためには、絵コンテを小さく描くべきという、経営的な判断を下したわけです。
しかし、その小さな絵コンテ用紙で描いていくうちに、宮崎監督は「こんなんじゃ、描きづらい!」と言い出します。Bパートまでは小さな絵コンテで描きましたが、Cパートからは従来通りの大きな絵コンテに戻りました。結局のところ、元の木阿弥となります。
絵コンテ全集のAパート・Bパートが、近藤義文監督によって清書されているのはそのためです。
楽しそうなことは自分でやりたがる宮崎駿
そして、宮崎監督は、絵コンテを描いていくうちに、劇中に登場する主人公・雫の作ったお話『バロンのくれた物語』の部分を、「自分で演出する」と言い出します。
宮崎監督は、画家の井上直久さんが描く「イバラード」の作風が、この雫が作った世界観にぴったりだと考えました。宮崎監督は、『耳をすませば』の美術監督の黒田聡さんに、「こんな感じで、やれないですか?」と、作風を真似できないか頼みます。しかし、黒田さんは、「ハイ、ムリです」と返答。スケジュールの都合もあって、難しかったようです。
そこで、鈴木さんは、井上さん本人に頼むことを提案しました。こうして、井上さんの協力のもと作ることになります。そして、外部のクリエイターが入ることによって、宮崎監督の介入も、若干弱まることになりました。鈴木さんとしては、一石二鳥だったかもしれません。
そうこうするうちに、当初言っていた「小品」のクオリティを遥かに超えて、大作に近い作品となって公開することになります。当時の配給収入で、18.5億円。現在の興行収入に換算すると、30億円程でしょうか。このときのスタジオジブリ作品としては、ヒット作品となります。
そして、なによりも、この作品は、ファン層を拡大していき、聖地巡礼が未だに続く、愛される映画になっていくのです。
 |
近藤喜文の仕事 動画で表現できること 近藤喜文さんの残した仕事を、後世に伝えるために製作されたものです。 一般の書店では扱っておらず、現在は『近藤義文展』などで販売されています。 |