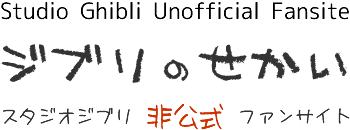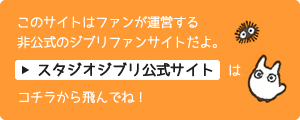2016年に公開された、スタジオジブリの最新作『レッドタートル ある島の物語』。アカデミー賞短編アニメ賞など、世界各国の映画賞を受賞した経験をもつマイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット監督を迎えて製作された長編アニメーション。ジブリ作品としては、初めて外国人監督を起用して作られました。
2016年に公開された、スタジオジブリの最新作『レッドタートル ある島の物語』。アカデミー賞短編アニメ賞など、世界各国の映画賞を受賞した経験をもつマイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット監督を迎えて製作された長編アニメーション。ジブリ作品としては、初めて外国人監督を起用して作られました。
2016年の公開に先駆け、マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット監督が外国特派員協会にて、海外記者の質問に答えました。こちらのインタビューを文字に起しました。
スタジオジブリから依頼があって、なにか誤解があると思った。
――世界中のアニメーターが仕事をしたいと思っているジブリで作品を作ることになったきっかけはなんですか?
マイケル:
ヨーロッパで私がいつも一緒に仕事している同僚はみんなジブリの熱心なファンです。始まりは突然、「ジブリで長編を作ってみないか? ジブリが製作をし、フランスの会社ワイルドバンチも共同で入ります」とジブリからメールが届いたことです。まず「もちろんやりたいです」と答えた直後に、ひょっとしたら、なにか誤解があるかもしれないと思って「ちょっと待って! 『一緒に仕事する』ってどういうこと?」と聞いたんです。
その後、ロンドンでワイルドバンチの社長と会って話す機会があり、そのときも信じられずに「本当の話なんですか?」と聞いたら「確かにジブリは、君に興味を持っている。ただ、いまの時点で絶対に作品を作ると約束したわけじゃない。そこで何か描いてもらい、ステップバイステップでそこから検討しようということになっている。」と。
――セリフがまったくない作品ですが、それは当初の予定通りだったのですか? それを決めたとき、周囲のスタッフの抵抗はなかったですか?
マイケル:
当初、少しだけセリフのある作品として構想していました。実際、少しはセリフがないと、ストーリーが伝わらない恐れもあったし、特に終盤、キャラクターの人間性を強調するために若干のダイアログが必要だと思いました。
ただ、その時点で少し違和感があったのも事実です。脚本作りの段階で、共同作業の中で、セリフを足したり引いたりするときでも、少しはセリフを残す方向で進めていました。
でも、脚本の開発を終えて実際に制作に入る前に少し時間があったんです。その段階で、出来上がっていたのはライカリールという、絵コンテをつないで作品の全体像が大体わかるもので、それをジブリに送ったんです。そうしたらジブリの方々がこれを見て、検討したところ「この作品はセリフは必要ないんじゃないかという結論に至った」と。ぼくは「少しは必要では?」と意見を言ったけれど「これはセリフがないほうが強い作品になるだろう」と。それを聞いて、ぼくは安心しました。セリフがない作品というのは、観客にとって違和感があるかもしれないし、作品として怖いところもあるけれど、そこまで信じてくれたジブリがいて、安心しました。声優が入るとなると、収録のときに、いろんなこと試してみるんだけれど、キャラクターが息をするときを演じてもらうと、どんなセリフより息が強調されて、人間性が伝わってきたように感じました。それもまた、本作はセリフがなくてよかったと思える部分でした。
ジブリに共通するものは、繊細さと大人っぽさ。
――この作品を観て、ジブリっぽいと感じましたが、ジブリのテイスト、美学がありますか? また、それを意識して作ったのでしょうか?
マイケル:
ジブリの特定の美学というものはないと思うけれど、宮崎駿さんの独特の美学、高畑勲さんの独特の美学というものはあると思います。ジブリに共通するものがあるとすれば、繊細さと大人っぽさであると思います。
でも今回、それを模倣しようとする意図は全くありませんでした。ジブリの人は、まずぼくの短編『父と娘』を観て絶賛してくれて、「日本らしい特徴を持っている。今回は自分のスタイルで描いてもらえれば大丈夫」と言ってくれました。
ぼくの作品とジブリの似ているところは一種の繊細さ。『ホーホケキョ となりの山田くん』は、俳句のような繊細さがあり素晴らしかったし、自分が目指すものもそこだと思います。テーマとしては自然への敬愛、その中での人間の在り方。そういう部分は、ぼくが目指すところでもあります。そんな難しい話は別として、ぼくもジブリが大好きだし、直感的な部分でピンときて、すごく仕事がやりやすかったです。
――普段から監督の作品はセリフが少ないということですが、どういう基準でセリフの必要性を感じているんでしょうか?
マイケル:
「映画」という言語が強く主張し、音楽やいろんな要素で表現できるので、短編作品でセリフがないものは、わりと多いし、必要ないことが多いんです。特に今回、長編ですが無人島なので話す必要がないというのがありました。
『キャスト・アウェイ』のトム・ハンクスみたいに、無人島でも一人で話し続ける必要はなかったんです(笑)。ただ、他の作品において、セリフがあることで得るものはあると思うし、今後、そういったこともありうるかもしれません。どういう作品を作っていくことになるかはわからないですけれど。
理性も必要だが、フィーリングが重要。
――最後のシーンによって、この作品のムードが変わると思いますか?
マイケル:
エンディングに関してですね。その質問には間接的な形でお答えしたいと思います。私は基本的に直感から物語を構成し始めます。理性も必要ですが、フィーリング、自分で強く感じたもの、アイディアや絵から「これだ!」と感じたものを描いていきます。そこから一歩踏み込んで、「これが観客に伝わるものか?」「この作品にあてはまるものか?」を判断し、もう少し論理的に作り上げていくのです。
この作品のラストに関して、感動的ではあるが非常に静かでシンプルなエンディングを求めていました。過剰に劇的ではなく、自然にスーッと入ってくるものがほしかったんです。直感で感じたものが正しいと信じて、そのまま作って大成功……という流れになれば簡単ですが、長編映画はそんなに簡単ではありません(笑)。
それが何万人もの観客にどれくらい伝わるかを考えないといけないので、絵コンテの段階から、いろんな人に見てもらい、反応を確かめました。その過程でジブリの方々が観て「伝わっている」と確信につながったし、ワイルドバンチのプロデューサーにも観てもらいました。制作段階では、アニメーションスタッフも加わります。こちらから「どう思う?」と聞いても答えがちゃんと戻ってこないことも多いけれど、コメントや反応から察したりして作り上げていく次第に「このエンディングで正しい」と確信しました。
――セリフがないだけでなく、クローズアップのショットがあまりないのはなぜ?
マイケル:
個人的な趣向、スタイルという側面も強いけれど、自分の作品、特に本作ではキャラクターはその環境にあってこその存在だと感じていたので、あまりクローズアップは使わず、どんなシンプルな背景だろうと、どういう環境にいるキャラクターなのかを描こうと思いました。
しいて言えば、バストショットはあるけれど非常に少ないですね。もう一つの理由は、普通、人が互いに話し合うとき、相手の目を観察したり、口を見たり、声を聞いて相手を読み取ろうとします。それは、日常で我々がする自然なことですが、アニメの動きでそれを表現するのは難しいんです。だから私の作品では、あえてそこまで表現せず、むしろ体全体を見せ、手の動きやボディランゲージ、顔の角度から表現しようとしています。
無人島のモデルはセーシェル諸島。
――環境が効果的に描かれていて、それはジブリ的な世界と似ています。細部にわたって世界を作っているのが感じられます。「この島はどこだ?」と思うけれども、どこかにリサーチに行ったんですか?
マイケル:
実際に島に行き、写真や動画を撮っています。実際、セーシェル諸島に行って島の雰囲気、海の雰囲気を吸収しました。この島の岩が特徴的で柔らかく丸い岩なんですが、それを気に入ってたくさん写真を撮りました。夕焼けや生物も観察しました。夜、浜辺を歩いたりもしましたね。くわえて滞在中、ぼくが高熱を出して寝込んだことがあって、幻覚を見たりしたんですけれど、そういうこともこの作品に適しているなと思って、興味深く受け止めていました。
ぼくはアニメーションの先生もやっているんですけれど、学生たちに教えるとき、「リサーチは楽しくプラスなことだ」と教えています。想像の中から「こういうものがいい」と決めても、実際のリサーチで動きを観察すると、予想できなかったことがプラスされることがあります。例えば、島の竹林はどうやって思いついたか? 普通は無人島だとバカンスのチラシとかパンフレットにあるヤシの木がスタンダードですよね? でも、この作品ではそういう典型的なイメージから離れたものを作りたくて、それなら竹藪を使ったら効果的なんじゃないかと思ったんです。実際、無人島で食べ物を調達しないといけないという点で、少しはヤシの木も必要でしたが(笑)。竹林に関しては、京都、日本の南部、そしてフランスの竹林をモデルにしています。
海外監督とのコラボについて。
――鈴木プロデューサーに質問です。ジブリにとって初めての海外の監督とのコラボレーションとなりましたが、今後もそういう可能性はあるのでしょうか?
鈴木敏夫:
今回のマイケル監督は特別だったという気がします。これまで、ぼくも仕事でいろんな海外の方とご一緒したり、親交を持ったりしてきましたが、とにかくプロデューサーとして彼の短編『父と娘』が大好きで、そのマイケル監督が長編を作ったらどうなるのか? その好奇心だけで今回の作品が出来上がったんです。これをきっかけに今後もどんどんやっていくかと言えば、今後、またそういう出会いがあるかどうか次第ですね。
――なぜ制作に10年も費やしたのでしょうか? 海外配給はすでに決まっていますか?
マイケル:
なぜ10年もかかったのかというと 実際の制作期間は3年ですが、その中でスタジオでアニメーターたちと共同作業をする前に、ストーリーを開発して固めないといけません。制作に入ってから変更があれば、コストや時間に無駄が出てしまうので、まず物語を完成させないといけなかったんです。あらすじを書くのは数ヶ月で済んだけれど、絵コンテを書いてライカリールを描く作業で、何千枚もの絵コンテを描いていくのは、ぼくにとって初めてのことでした。そこで描いたときにいいアイディアと思っても、実際に絵コンテをつなげてみると成立していないこともあったりしました。基本、強い作品ができたと感じていましたが、課題が残って、どう解決したらいいかわからない部分もいくつかありました。「どう組み直したら観客を引き込めることができるか?」そういったことを考えました。
また、海外配給に関しては、すでにフランス、ベルギー、オランダ、スイスなどで公開されており、日本でもまもなく公開ですし、欧州はもちろん、今後、北米や南米にも広がっていくことになります。
津波のシーンは、震災前から考えていた。
――映画の中で津波の描写がありますが、波が突然、引いていくシーンを観て、多くの日本人が、やがて津波が来る予感を感じると思います。このシーンは最初の段階からあったんでしょうか? 東日本大震災の津波被害のことがあった後で意味を持ってあえて入れたのでしょうか?
マイケル:
あのシーンは、2007年から2008年の絵コンテの段階ですでに考えていました。数年後に東日本大震災があり、ニュースで津波のことを知って、ジブリの方々に「このシーンを描くのは違和感があるのでは? ジブリとしてどう思うのか? 日本人はどう感じるか?」と聞きました。ジブリの方の答えは「もちろん、センシティブなシーンだけれど、作品の中での重要性は感じていて、鈴木プロデューサーも高畑さんも『残すべき』と考えている。特に作品の中で漫画っぽく、面白おかしく描かれているわけではなく、リアルな津波が襲ってくるさまが描かれていて、リスペクトもあるから大丈夫だろう」というものでした。
今回、ジブリ展の準備で来日した際、ある日本人のスタッフと東日本大震災の話をしたら、彼は震災の六ヶ月後、叔父を探しに被災地に向かい、被害を目の当たりにしたと教えてくれました。彼は、「この映画の中での津波シーンは、非常に感銘を受けるシーンであり、このシーンがあるからこそ、日本人はこの映画を観るべきだ」と言ってくれました。
 |
レッドタートル ある島の物語/マイケル・デュドク・ドゥ・ヴィット作品集 『レッドタートル ある島の物語』をはじめ、『アロマ・オブ・ティー』『父と娘(旧題:岸辺のふたり)』『お坊さんと魚』『掃除屋トム』『インタビュー』 を収録。 |